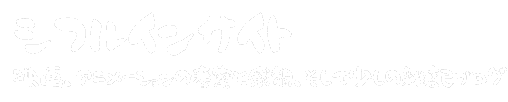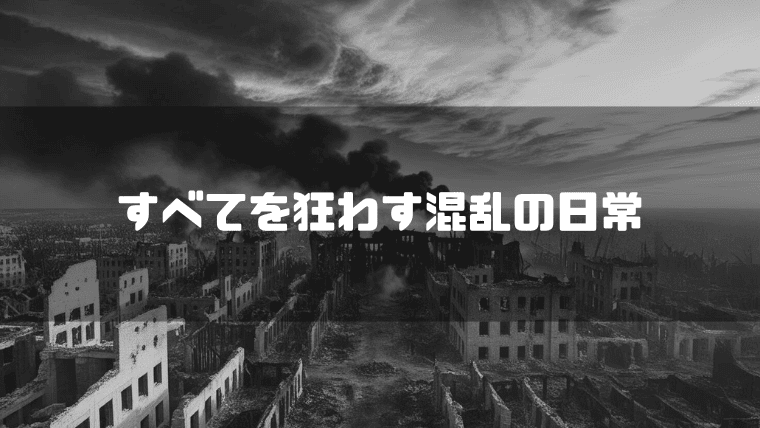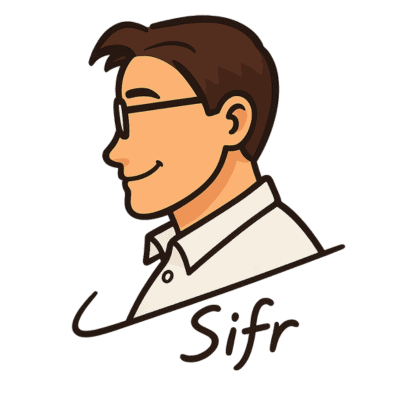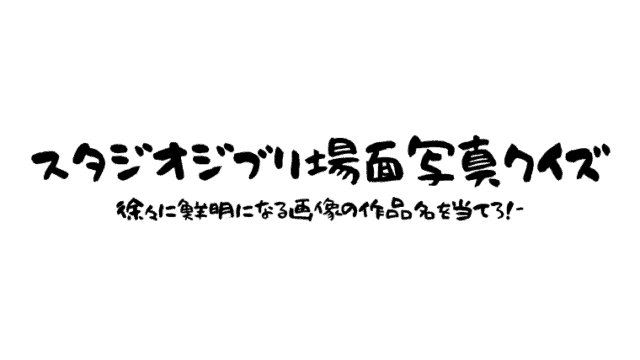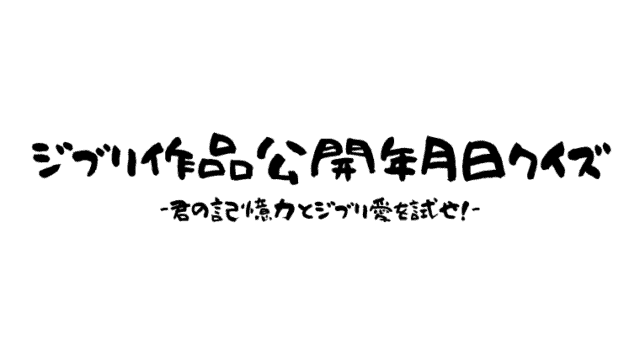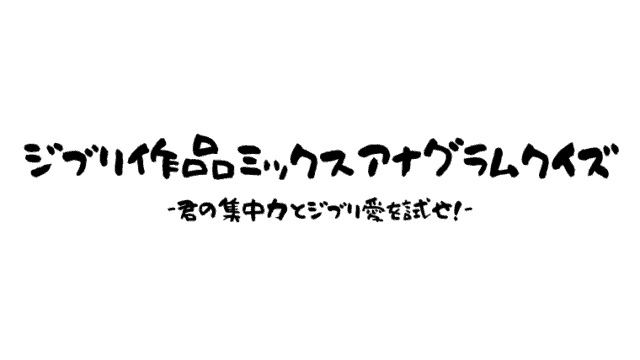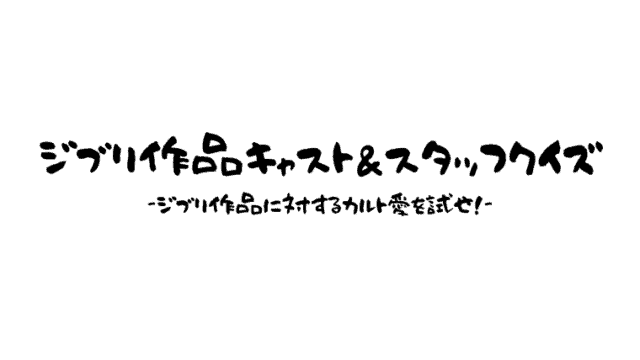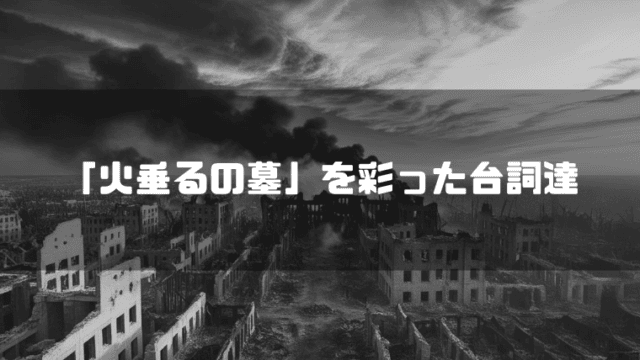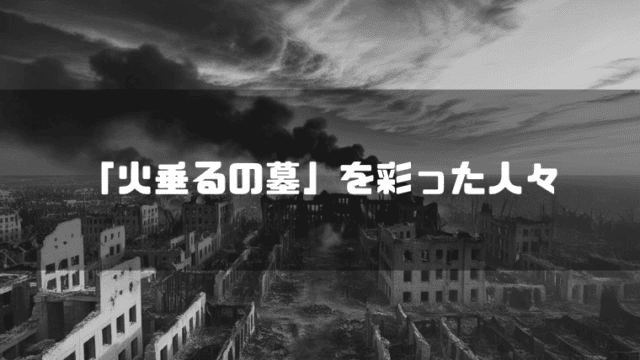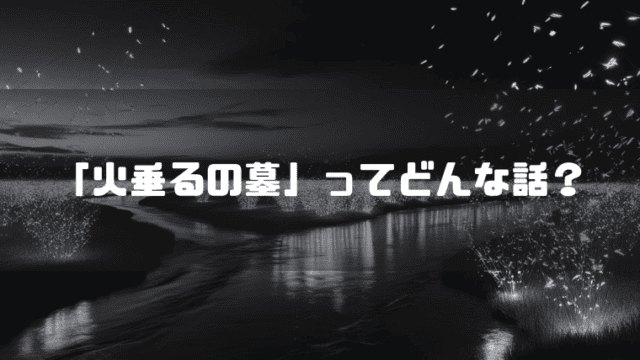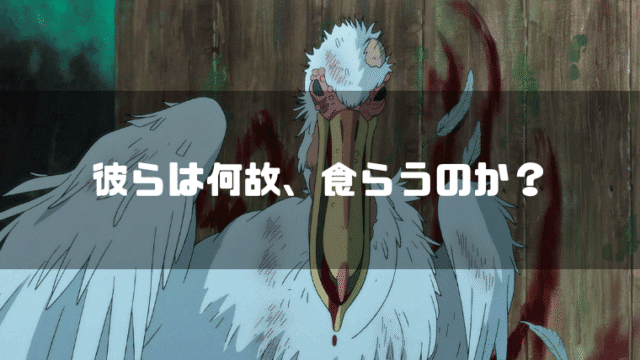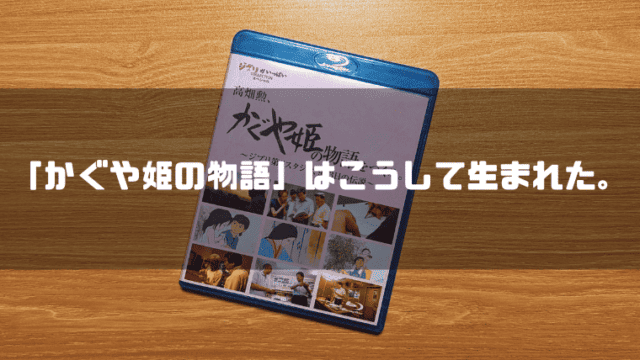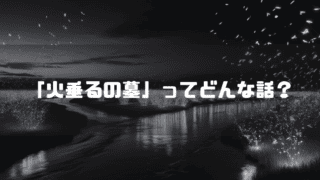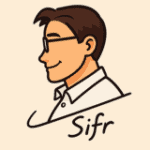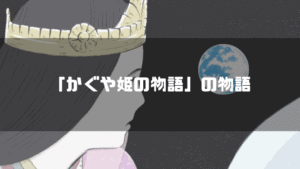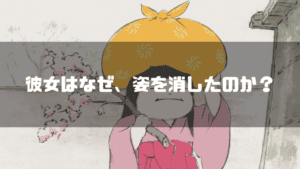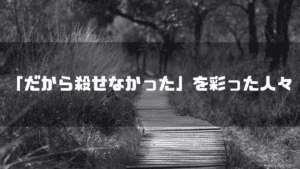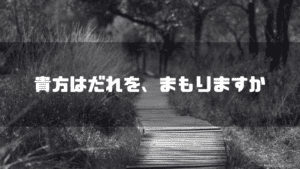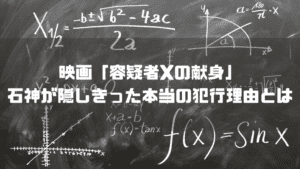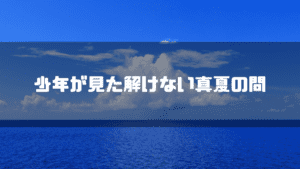「火垂るの墓」は1988年に公開された高畑勲監督による劇場用アニメーションである。
これまでジブリ作品だけでなく、いろんな作品についての文章を書いてきたが、「火垂るの墓」についてはどうしても思考が形にならなかった。
映画の感想としては「戦争は悲惨」で十分だし、何度も何度も見る映画でもない。その一方で、「戦争は悲惨」で終わることのもったいなさもあったのだが、ようやく自分の中で書くべきことがまとまったので今回はそのことについてまとめていこうと思う。
文章のフックとなる問いは、この記事のタイトルにあるように「清太と節子はなぜ死なねばならなかったのか?」である。
私達は清太と節子の死をどこまで考え抜くことが出来るだろうか。まずは「火垂るの墓」についての高畑監督の言葉を紹介しよう。
-
監督・高畑勲の言葉と作品への姿勢
高畑監督は「火垂るの墓」を 「全体主義への反抗」や「普通の子供の悲劇」の物語として位置づけつつ、 同時に「反戦アニメではない」「単なるお涙頂戴でもない」と語っている。 これらの発言の背景には「戦争をなくす方法」を提示することができていないということがあったのではと考えられる。 -
清太への批判と“後ろめたさ”
節子を道連れにした清太を責める気持ちは自然だが、 それに留まらず「周囲の大人も手を差し伸べなかった」点に 自分たちの後ろめたさを投影している可能性がある。 「困っている人を無視しているのでは」といった 現代社会への問いにもつながる。 -
閉じた世界=“心中もの”としての構造
監督自身が「いかに死に向かっていったかを閉じた世界で描く」 という点で本作を「心中もの」と捉えていた。 清太が一方的に節子を巻き込んだように見える反面、 節子の存在が清太の死を加速させた側面もあり、 相互に破滅へ進む“無理心中”の様相を帯びている。 -
戦時下の日常と“民俗学的資料”としての価値
戦争末期の混乱のなかにも銀行が機能し、 普通の生活や子どもの遊びがあった事実を丁寧に描くことで、 フィクションながら“当時の暮らし”をリアルに証言する側面がある。 高畑監督の空襲体験を基盤に、 “ドキュメンタリー的”意味合いを含んだ作品となっている。 -
孤立は“死”を招く—人との繋がりの重要性
清太が“情報弱者”となり終戦を知らず、 社会から切り離されたことで節子とともに破滅へ向かった構図が示すように、 「人は人と繋がりながら生きねばならない」という普遍的メッセージを孕む。 監督が「いつか社会が再逆転するかもしれない」と恐れたのは、 結局、人間同士が手を差し伸べない世界が再来することへの警鐘ともいえる。
「火垂るの墓」の考察
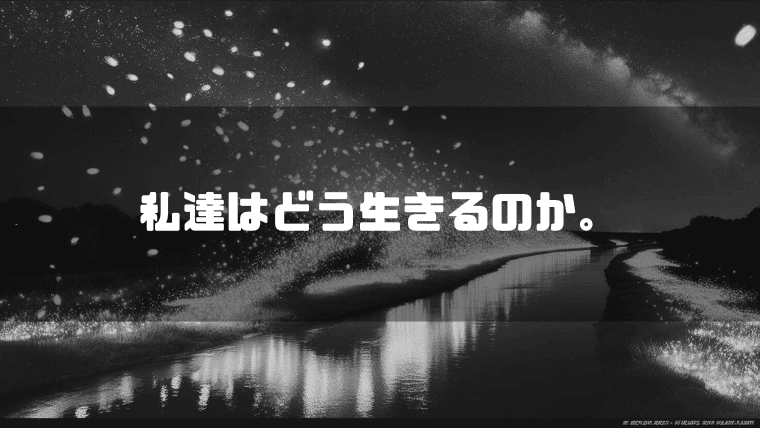
高畑勲の言葉
映画に限らず、物語を作った人の言葉というのは重いもので、私としてもとても気になる。そして、「火垂るの墓」の監督である高畑勲監督の次の言葉はよく引用される重要な証言となっている:
当時は非常に抑圧的な、社会生活の中でも最低最悪の『全体主義』が是とされた時代。清太はそんな全体主義の時代に抗い、節子と2人きりの『純粋な家族』を築こうとするが、そんなことが可能か、可能でないから清太は節子を死なせてしまう。しかし私たちにそれを批判できるでしょうか。我々現代人が心情的に清太に共感しやすいのは時代が逆転したせいなんです。いつかまた時代が再逆転したら、あの未亡人(親戚の叔母さん)以上に清太を糾弾する意見が大勢を占める時代が来るかもしれず、ぼくはおそろしい気がします
これ以外にも高畑監督は「火垂るの墓」についてのコメントを残しており、現在ではWikipediaの「火垂るの墓」を見るだけで上記以外の言葉を知ることができる。
例えば、
「反戦アニメなどでは全くない、そのようなメッセージは一切含まれていない」
「本作は決して単なる反戦映画ではなく、お涙頂戴のかわいそうな戦争の犠牲者の物語でもなく、戦争の時代に生きた、ごく普通の子供がたどった悲劇の物語を描いた」
などである。これらは引用元も明らかにされているのでコメントとしては正しいものと認識して良いと思う。
ただ、我々に取って深刻なのは、これらのコメントは一見矛盾しているように思えるということ、そして、自分にとっての「火垂るの墓」の感想とも何やら齟齬があるように思われることである。
しかし、私の考えではこれらのコメントに矛盾はない。その辺の事を考えていこうと思う。
清太の「わがまま」を責める思いの裏側にあるもの
「火垂るの墓」を真っ当な知性を持っている人が見れば、恐らく清太を責めたくなるだろう。そしてその理由の本質は、節子を道連れにしたということになると思う。
それはそれで正しいことであって、私もそう思う。
しかしだ、清太はともかく、節子だけなら救える人はあの物語の中に何人もいたのではないだろうか?
最初に身を寄せた叔母さんだって、清太を良くは思わなかったかもしれないが、「節子はおいていきなさい!」の一言があってもそこまで違和感はなかったと思う。
そして、清太と節子が穴蔵で暮らすことになってからも、二人に手を差し伸べる者はいなかった。
当然そこには「戦争末期で、みんな自分のことで手一杯だったから」という理由づけがあるし、その通りだと思う。
だが、そのように物語中の人々の行動を擁護することと清太とを非難することの間には絶妙な差があるように思える。
つまり、戦争状態にない現代においても、自分が清太のような人々を見殺しにするかもしれないという思いがどこかにあるのではないだろうか?
その理由ならいくらでも作ることはできるだろう。私達だって自分達のことで手一杯でないということもない。日々の生活、仕事があり「あのとき声をかけておけばよかったな~」と自分の正義を殺してしまった後悔の経験もあるだろう(もしないならGreat!)。
そして、私達はそんな自分のあり様に「後ろめたさ」をわずかに覚えてもいる。「確かに自分事で大変だけど、手を指し飛べられないほどでもなかったと」。
その「後ろめたさ」を隠したいがために清太に対して攻撃的になってしまう側面もあるのではなかろうか。
高畑監督が「おそろしい」と感じたものと苛烈な「シミュレーション」
人としての根源的な「やさしさ」
結局、高畑監督が「おそろしい」と感じた社会になってしまったのだと思うが、それは単に「火垂るの墓」をどのように評価するのかということではなく「後ろめたさ」を感じていながら困った人に手を差し伸べなくなった社会ということではないだろうか。
別の言葉で述べるなら、「困っている人を助ける」という根源的な「やさしさ」がなくなっている、あるいはそれを発揮できなくなっている社会とも言えるかもしれない。
高畑監督は9歳の時に岡山で空襲にあっている。その時、ひとつ上の姉と二人きりで市街地を逃げ惑い、近くの川沿いで雨に打たれながら夜が明けるまで過ごした(参考:「高畑勲監督の対談をご紹介【月刊『同朋』誌2015年8月号より】」)。
その時に目を合わせながら自分を無視した大人がいたかどうかはわからないが、強烈な孤独であったことだろう。
そして、多くの人々の衣食が実のところ足りていて、焼夷弾から逃げ惑わなくて良い社会ですら、川沿いで孤立した9歳の少年とその姉に手を差し伸べなくなったと思えば、それは恐ろしいだろう。
ただ、このように考えると一つの疑問が湧いてくる。言い方は悪くなるのだが、それならもっと早く清太と節子が悲劇を迎えたほうがその「おそろしさ」がわかるように思える。なぜ清太と節子は穴蔵である程度の日々を送れてしまったのだろうか?
私が思うに、あれは高畑監督による苛烈なシミュレーションだったのだと思う。あの日、あの時、他の家族が全員亡くなり、子供だけになったとしてどこまで行けたのか。それを本気でやってみようと思ったのではないだろうか。
もちろん「火垂るの墓」は野坂昭如の原作があるわけだが、それを映画化しようと思えた理由がこの「シミュレーション」にあると思える。
しかもこれは「じっさいどこまでいけたかな~」というぼんやりしたものではなく、「じゃあやってやるよ。手を差し伸べないならやってやるよ!」という苛烈なものだったと思う(と受け取った)。
しかし、高畑監督は夢想家ではない。程度の低いファンタジーで人々を翻弄したいわけでもない。きちんと地に足つけて物事を考えれば、その行く末が破局であることは明白であったわけである。
つまり、高畑監督は言いたかったのではないだろうか「な?どんだけ頑張ってみても無理なもんは無理だろ?もちろん、清太と節子に限って言えば、我慢できなかった清太が悪いだろうよ。でもさ、現代ならどうなのさ。困っている人が悪いのかい」と。
希望としての「おにぎり」
さて、高畑監督の言わんとするところはわからんではないのだが、「火垂るの墓」という映画はそれにしても救いがなさすぎる。
ただ、この救いのない映画の中にもたった一つ希望の光が描かれている。
物語のスタート時、清太はボロ雑巾のような姿で駅の構内にいた。そんな清太を通り過ぎる人々はそれこそ汚物を見るような目で見、そして扱っていた。
そんな中、たった一人だけ、清太におにぎりを渡す人物が描かれるのだが、私はそのシーンを見ると強烈に涙があふれる。
全く持って救いのない悲惨な物語の中にある唯一の救いである。
高畑監督は、「困った人に『おにぎり』をあげられるような生き方をしましょう」と言っているのではないだろうか。言葉にするとなんとも単純だが、それを丁寧に作られた映画の中で表現されるので我々の胸に突き刺さるのである。
なぜ「反戦映画」ではないと発言したのか-「民俗学的資料」としての「証言」-
ここまで色々考えては来たが、我々を最も困惑させる高畑監督の言葉について考えていこう。つまり、「反戦アニメなどでは全くない、そのようなメッセージは一切含まれていない」と高畑監督が発言した意図を考えていこう。
これには主に2つの観点があると思う。一つは「How to」にはなっていないということ、そして、あれは「自伝」であるということ。
戦争をなくす方法論までは提供出来ていない
我々が高畑監督の思いを類推するうえで、最も需要な視点は「私達は『反戦』ではない物語を見たことがない」ということだと思う。すくなくとも、1945年以降。
逆に聞きたい、あなたが見た「反『反戦物語』」を!
我々が生まれてきてからこれまで見てきたすべての物語は「反戦」である。それ以外の物語など見たことがない。というか、そんなことは当然のこととして、さてどうしますか?という物語に包まれてきたと思う。
つまり、高畑監督が「反戦映画」を作るなら「How to finish the war in the world」まで描くと思うのだよね。
それを作れなかったから「反戦映画」ではないと答えてのだと思う。
高畑監督の判断基準における「反戦映画」の基準は「戦争はよろしくない」とい当然のことを描くことではなく、このようにすれば戦争はなくなりますという方法論までを提示する作品ということになるのだろう。しかもそれは「ファンタジー」であってはならない。
だから高畑監督は「反戦映画ではない」とコメントしたと考えることが出来ると思う。
自伝、そしてドキュメンタリーとしての「火垂るの墓」-映像化がなせる技-
「火垂るの墓」が戦争をなくすための「How to」になっていないという視点がある一方で、あれは高畑監督にとっての「自伝」であったと見ることが出来るだろう。
その思いは「戦争の時代に生きた、ごく普通の子供がたどった悲劇の物語を描いた」という言葉にあらわれていると思う。
岡山で実際に空襲を受けたことや、姉と二人きりで逃げ惑った経験に伴う「気持ち」の部分を噛み締めてほしかったのだと思う。
その結果として我々が涙を流したり「反戦」の思いを持つのは構わないことだが、それを第一の目的とはしていなかったということも出来るかもしれない。
勿論「火垂るの墓」は野坂昭如の小説を原作としたものであるが、その原作の中に「リアル」を感じたからこそ高畑監督は映像化する価値があると思ったのだろう。
また、アニメーションだからこそ、そのディティールを映像として観客に追体験させることが出来るという事もあっただろう。
実際問題として戦争末期の人々がどのように生活していたのか。それはどれほど過酷でありかつ普通であったか。
当時を知っている人ならば、小説としての「火垂るの墓」を読んでもそれを補完できるが、そうでない人間はそれが出来ない。丁寧に丁寧にそれをアニメーションとして描写してくれたおかげで、私達は戦争末期の状況を知ることが出来るわけである。
そしてその指揮を取れるのは、やはり当時を知っている人間。
結局、「自伝」という側面をもたせることが出来る人物であるからこそ「火垂るの墓」は映像作品としても意味を持つものになったのだと思う。
そしてその結果、映像作品としての「火垂るの墓」は過去を描くドキュメンタリーになっている。
もちろん「火垂るの墓」はフィクションである。野坂昭如の実体験に基づくフィクションである。
だが、そのフィクションを高畑勲が映像化したことが我が国の幸運であり、重要な映像資料ともなっているのだと思う。人々の生活を丁寧に描いてきた高畑勲だからこそ、「火垂るの墓」を正しく映像化出来た。
また、小説を映像化することの意味合いを考えると、「火垂るの墓」をアニメーションで表現したことには大きな意味がある。つまり、当時に戻ってカメラを回すことは出来ないのだから、ある種の「ドキュメンタリー」として映像化するならアニメーションの方が向いていることになる。
それを実行するには多大なる苦労があったとは思うけれど。
「火垂るの墓」は公開当時2箇所ほど色が塗られない状態であったという逸話(?)がある。高畑勲という人物はすでに決まっている公開日に間に合わせるという気が全くのない人で、とにかく映画のクオリティにこだわる人であった。そのため制作が遅れに遅れて色が塗られない状態での公開に至ったというわけである。
当時の関係者の方々は非常に苦労したと思うが、結果として「火垂るの墓」が名作になったわけなので、高畑勲には賛辞を送るべきだろう。周りの人は本当に大変だったと思うけど。
しかし、その多大なる苦労と犠牲の結果として「火垂るの墓」は「民俗学的資料」になっているという側面がある。
過去(歴史)を知る方法論としては「史学(文献調査)」「考古学(発掘調査)」そして「民俗学(フィールドワーク)」があると思うが、「火垂るの墓」はこの内「民俗学」に属する資料にはなるのだと思う。
残念ながら「火垂るの墓」の描写も主観に基づくものになっている。したがって「史学」の対象にはならないし、勿論「考古学」の対象にはならない(1000年後に「アニメーション」という考古学的資料にはなると思うが)。
しかし、重要な証言としての「民俗学的資料」にはなる。
実のところ不正確なところはあると思うのだが、我々が「火垂るの墓」を通じて知ることの出来る「民俗学的事実」としては
- どうやら銀行は機能していた。
- 苦しいけれどもなんか普通の生活があった。
- 医者にかかることも出来た。
- 子どもたちはパヤパヤと遊んでいた。
といったものがあると思う。教科書を読んでいると終戦間近というものは「暗黒の日々」なのだが、どうやらそうでもないらしいことが「火垂るの墓」の映像表現によって分かる。もちろんこれらのことは多くの批判にさらされなければならないのだけれど、一つの「証言」ではある。
わざわざ野坂昭如の小説を映像化するモチベーションの中にはこのような「民俗学的資料」あるいは「証言」を残すという思いがあったのだと思う。そういう意味においても「反戦映画ではない」といったのだろう。つまり、「これは証言である」という意味合いもあったのだと思う。
ただし、「火垂るの墓」で描かれたことを全部資料として受け入れてよいかといえばそうとも言えないというところもあり、例えば神戸大空襲のシーンで描かれた焼夷弾については不正確であると見ることも出来る。この件に関しては以下の記事でまとめている。

重要な資料ではあるのだが「過去」を描いた作品を見るときには注意が必要である。
清太はなぜ駅の構内にいたのか?
「戦争映画ではない」という発言についてわずかに関係するトピックスとして、映画のスタート時に清太がなぜ駅の構内にいたかも考えたい。
映画本編で見てきたように、彼は節子と横穴(防空壕)生活を送っていたのだから普通に考えると節子のようにそこで生涯を終えても良さそうなものである。
彼が駅の構内にいた理由のヒントは、映画のスタートを飾った「昭和20年9月22日夜。僕は死んだ。」という台詞だろう。
先に述べたように節子の命日はその1ヶ月前の8月22日。清太は節子の死後1ヶ月生き延びたことになる。
その間彼は何をしていたのだろうか?
彼には親の貯金という秘密兵器があったが、お金があったところでどうにもならない状態にあったことは本編でも描かれていた。
しかし、ただでも栄養を取れていない14歳の少年が、飲まず食わずで1ヶ月生き延びることはできないだろう。
つまり彼は死なない程度には食べていたのである。
しかし、お金は役に立たなし、コミュニティの中で生きるチカラはない。つまり彼は、盗みなどを働きながらその日暮らしをしていたということになるだろう。
そして、盗む場所がなくなったのかその気力がなくなったのか、物乞いに転じたと考えられる。
物乞いをするなら人が多いほうが良いので、彼は駅の構内にその「本拠地」を移したと考えられるのではないだろうか。
ここで見えてくるのは、なんやかんや生き延びようとする人の根本的な行動原理である。
彼は節子の死という絶望の中でも腹が減り、そして腹が減れば何かを食べようとしたのである(誰だってそうなるさ!)。
そしてそういった人間の本質が清太の生き延びた1ヶ月に象徴されているし「昭和20年9月21日夜。僕は死んだ。」というオープニングの台詞に凝縮されているのである。
「火垂るの墓」には勿論「戦争」という要素があるのだが、清太と節子の生き様を描くことで「人間とは」ということも描こうとしたのではないだろうか。
そういったところも、高畑勲監督が「戦争映画ではない」と発言したことにつながったと思われる。「戦争」以上に見てほしい部分があったということだろう。
一応言っておくが、節子の死後に清太に死んでほしかったなんて思っていない。そういう考え持つ年齢ではもはやない。彼には1日でも長く生き延びてほしかったと心から思っている。
「心中もの」という言葉
ここまで来たので、高畑監督以下の言葉についても個人的な考えを述べてみようと思う:
野坂昭如さんの原作にひかれたのは、2人がいかに死に向かっていったかを閉じた世界の中で描くという「心中もの」の構造があったこと。アニメなら新しい求心力で描けるのではないかという表現上の野心が強かった。
空襲の経験、きちんと映画に 「火垂るの墓」高畑勲監督より
問題にしたいのは勿論「心中」という言葉の意味となるのだが、残念ながら「表現上の野心」については今のところ自分の言葉になってはいない。そのかわりに「2人がいかに死に向かっていったかを閉じた世界の中で描く」という観点で高畑監督が「心中もの」を描こうとした意図を考えていこうと思う。
「心中」の持つ一方向性と破滅
本来的に言うと「心中もの」というと、男と女が双方の同意のもとに「来世ではせめて・・・」という物語のことである。
しかしだ、そんなこと現実で本当に発生するのだろうか?まあ、発生したのだろうけれど、大事なことは、二人の人間が死んだという事実からそれが「心中」であるとはどのように判断するのだろう。
ここで私が言いたいのは、「心中」は「無理心中」であることが多いのではないかという勝手な推論である。
人間が二人いれば、そこには何かしらの上下関係がうまれるもので、ある人にとっての「心中」が他方にとっての「無理心中」であることのほうが想像しやすいわけである。
そしてちょっと悪意がありすぎるのだが、高畑監督は野坂昭如の原作にその「一方向性」を見たのではないだろうか。
清太にとっての節子は「心中」の相手だったかもしれない。節子も清太といっしょにいたかったかもしれない。
しかし、清太は生き残り、節子は死んだ。そして結局清太も死んだ。
高畑監督の言うように、二人は「閉じた世界」で生きた。その結果として一方の思惑によって全滅している。
これを現代社会に置き換えればどうなるのだろうか?
手を差し伸べなければ、自分が死ぬということになるだろう。
俺達は実のところいつでも「無理心中」を強いているし強いられている。その立場は絶対的なものではなく状況によって変化する。
みんなで、なんとなく、ぼんやりとやっていく。これしかないと思うが、これが難しい。
どうしたもんかね。どうしたもんかね。残念ながら俺にはわからん。
「心中」の両方向性が生む客観性
さて、ここまで考えてきたことの背後には「清太が節子を道連れにした」という思いが明確にある。
それは否定しようの無いことなのだが、「心中もの」という言葉をもう一度振り返って見ると、「清太を死に追いやったのが節子」という見方だって出来る。
このような事をいうとひんしゅくを買うとは思うのだが、そう思ってみても良いから「フィクション」というものに意味があると信じて書き続ける。
そして、この「不謹慎な」ものの見方ができることによって「火垂るの墓」を客観的に見ることが出来るようになるだろう。
つまり、
- 清太はアホだが叔母も意地悪だったし、
- 節子を殺したのは清太だが、よく面倒は見ていたし、
- 二人の死は清太の自爆だが、社会は彼らに手を差し伸べなかったし、
- 考えたくないことだが、節子がいなければ清太は叔母の家に居続けられたかもしれないし、
- 節子は死んでしまったが、叔母の家にい続けるよりは満ち足りた生活だったかもしれない。
そもそも私達は清太が14歳の子どもであることを忘れがちである。構造上清太を責めることができたとしても、14歳の子どもに命の責任を追求するのは酷というものだろう(こんなことですら忘れがち)。
高畑監督は非常に頭の良い人なので、作品の中に「絶対的立場」みたいなものを作らないように工夫しているように思える。だからこそ輪達たちの中にある「正義」がゆらぎ、色々と思い悩んでしまうことになる。
「清太を攻めたくなるが、彼らを殺したのは社会だし、でも戦争中だからしょうがなし、清太ももっと我慢すべきだったし、とはいえ出来ることがあったのではないか・・・・」と。
高畑映画はきっとこれで良いのだろう。私達は思い悩むために高畑映画を見るのである。
すでに心が壊れていた清太と節子
「心中」という観点で最期に考えたいのは清太と節子の「心の傷」である。
清太と節子は4歳と14歳という年齢で神戸大空襲で死の恐怖を味わい、母の死を経験してしまっている。
特に清太は、大火傷を負って包帯グルグル巻きの母を見てしまったし、その遺体が「もの」のように扱われて、追悼とはかけ離れた火葬をされるところも見てしまっている。
14歳の少年に耐えられるものだろうか?耐えられなくても不思議はない。
清太の心の傷については以下の記事でもう少し詳しく考えている:
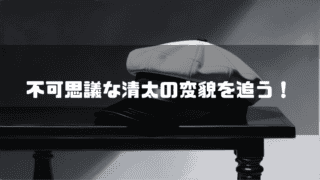
何れにせよ、清太と節子は大きな心の傷を抱えてしまっている。
清太がその傷を表に見せないものだから我々はそのことに気が付かないのだが、空襲と母の死を経験する前と後で14歳の少年やその妹になんの変化もないと考えるのは都合が良すぎるだろう。
つまり、清太と節子はすでに壊れていたのではないだろうか?
物語の序盤の清太を見れば、叔母の厄介になっているのに1日中ゴロゴロ寝ているなんてことは考えられない。でも、そうなってしまっている。
彼らが負った心の傷はコミュニティの中で人と関わる力を奪ってしまっていたのかもしれない。
「心中」とはつまり、現世に対する絶望や悲しみに基づく行動である。世界の有様が二人を排斥するのならわざわざその世界に執着する必要はないとあの世で結ばれようとするわけである。
戦争末期にコミュニティから弾かれることは死を意味したかもしれないのだが、そのコミュニティで人と関わる力を失ってしまっているものにとってはその世界そのものがその人に「死ね」といっているようなものである。
そして清太はそのように考えたから二人だけの世界に逃げ込んだし、その行動はまさに「心中」と呼ぶべきものだろう。
「火垂るの墓」を見るとどうしても清太を責めたくなってしまうのだが、彼の経験したことを考えれば大きな心の傷を負っていると考えるのが自然であり、その原因はまさに戦争である。
何かを責めたいのなら、その対象は清太ではなく、その心に決っして言えない傷を与えた戦争と考えるべきだろう。清太には「心中」意外の道が残っていなかったのである。
叔母さんを再考する
最後に、清太と節子の叔母についてもう少し考えていこうと思う。
叔母の苛立ちと「嫉妬」
実のところ、「火垂るの墓」という物語を実質的に推進したのは清太ではなくあの叔母である。彼女がファンタジックな慈愛の心を見せてくれればあの物語は存立し得ない。
となると、叔母はどうしても清太にとってよろしくない存在となる必要がある。
では、叔母はなぜあそこまで清太たちに辛く当たったのだろうか?
「清太がアホだったから」という言い方もできるし、そうでなかったとしても「単純に煩わしい」という気持ちがわからなくもない。戦争という混乱のなかで「少しはしおらしくしろ!」と思う気持ちはむしろ理解できてしまうだろう。
ただ・・・せっかくなのでもう少し勘ぐってみよう。
一つの根拠になりうるのは、清太と節子の父親が海軍大尉だったことだと思う。
当時は戦争末期であり、「兵隊さん」は即ち偉い存在となる。それが海軍将校なればいよいよ「偉い」ということになるだろう。
多くの人々が苦しい生活を強いられている中で、清太の家族は、意図せず比較的余裕のある生活をしていたかもしれない。それは金銭的なことだけでなく精神的な意味において。
そしてそんな清太に対して叔母がある種の「嫉妬」を抱いていても無理からぬことではないだろうか。
眼の前にいるのが守るべき子どもであることを分かりながらも、清太や節子の言動のあちこちから「海軍大尉の子ども」の臭いがぷんぷんしてしまった。
つまり、清太と節子の父親が海軍大尉であるという事実は「7000円の貯金」という事実の裏付けを与えると共に、叔母の二人へのきつい態度の根拠にもなっているということになると思われる。
作劇上の犠牲者としての叔母
さて、最終的には物語の最重要人物と言えそうな叔母であるが、メタ的な視点に立つと、彼女もまたある種の犠牲者と見ることが出来ると思う。
つまりあの叔母は、「火垂るの墓」という物語を成立させるために「意地悪な叔母」という憎まれ役をやらされているのである。
近年でこそ清太に対する非難が大きくなり、叔母の行動はむしろ同情を呼んでいる。
そんな状況になってしまうことを高畑監督は「おそろしい」と表現したし、それについては上の方で自分の考えを述べたわけだが、あの叔母としてみればどうだろうか。
「ようやく時代が追いついた!」といったところだろう。
もちろんこれはメタ的な視点に立った場合の話であり、あの叔母は戦後ひどく後悔したことと思う。
そして、あの叔母も戦争の犠牲者であるということを忘れてはならないだろう。
人は人と繋がりながら生きなくてはならない
「火垂るの墓」が我々の心に残ってしまう理由としては、勿論節子の非業の死が主なものになるだろう(個人的には包帯グルグル巻きの清太の母の姿のほうがデカかったが)。
ただ、その死そのものが悲しいとうこともあるのだが、清太が終戦を知らなかったという事実もその悲劇をより一層大きなものにしている。彼は叔母の家から出てしまったことによって現代的に言うところの「情報弱者」になっていた。
野坂昭如による原作小説によると節子の命日は8月22日である。もし清太が終戦を知っていたら、叔母に頭を下げることも出来たかもしれない。少なくとも彼の行動には大きな変化がもたらされたのではないだろうか(というかそう信じたいと思わせられる)。
そして、節子は生き延びることが出来たかもしれない。
もちろん節子の栄養失調の兆候は随分前から出ていたし、清太が生き方を変えたからと言って節子の死は免れなかったかもしれない。
それでもなお、「終戦」の一報が何かを変えてくれたかもしれないと思ってしまう。
どこまでもいたたまれない物語だが、清太が「情報弱者」となってしまっていた事実は、我々に「人は人と繋がりながら生きなくてはならない」という素朴なメッセージを象徴している。
これだって言葉で言えば簡単であるし、誰だって知っていることのように思える。しかし、そんなことを「火垂るの墓」という物語の中で突きつけられるから身につまされるのである。
90年代以降、我々は「コミュニティ」の持つ煩わしさから開放されようとしてきたように思える。それはある意味で「孤立」が「死」を意味しない成熟した社会になったということも出来るのだが、その一方、なお残り続けている「孤立」のリスクに気が付き始めているようにも思える。
我々人類が安定した絶対的なあり方に安寧する日はないのだろう。「繋がり」は「孤立」を生み出すし「孤立」は「繋がり」を求めることになると思う。結局「状況に対する反抗」でしか今は生み出されない。
そして、我々の社会がある種の「コミュニティ」を取り戻し「繋がり」という保険を再び手にしたときには、その状況に反抗した存在として清太が再評価されるのかもしれない。
未来のことは決してわからないのだけれど。
以上が「火垂るの墓」について私が個人的に考えたことでした。
一度見たら決して忘れることのできない物語としての「火垂るの墓」ですが、この文章は「考察」と称して発表した「感想文」でございます。みなさんは「火垂るの墓」をどのように捉えたでしょうか?
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年4月23日
【君たちはどう生きるか】大量のインコとペリカンは何を意味するのか-大王が象徴する宮崎駿と「俺達」- - 2025年4月15日
【シン・仮面ライダー】オーグメントの絶望の謎と「アイ」が隠した本当の戦略-本郷猛は何故勝利して良いのか- - 2025年3月25日
【侍タイムスリッパー】あらすじとその考察-椿三十郎の呪を打ち破る「究極の殺陣」- - 2025年3月2日
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」を見た感想と考察ーテム・レイの正しさとレビル将軍の行方ー - 2025年2月26日
「機動戦士ガンダム」スペースノイドの怒りと地球連邦政府という奇跡ー物語を支える3つの重要な側面を考察ー