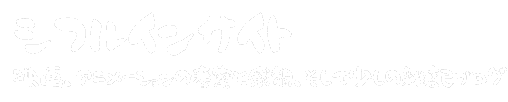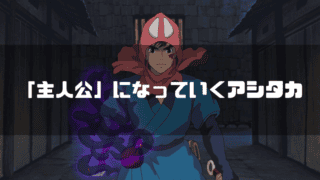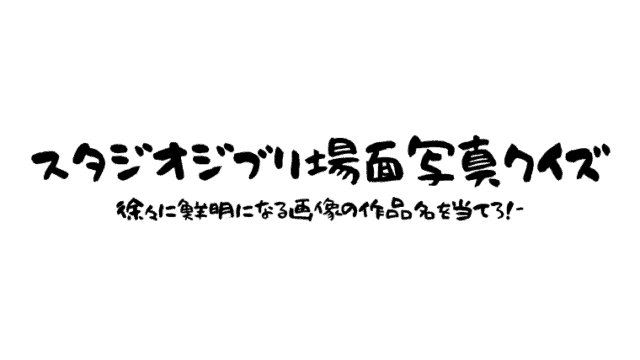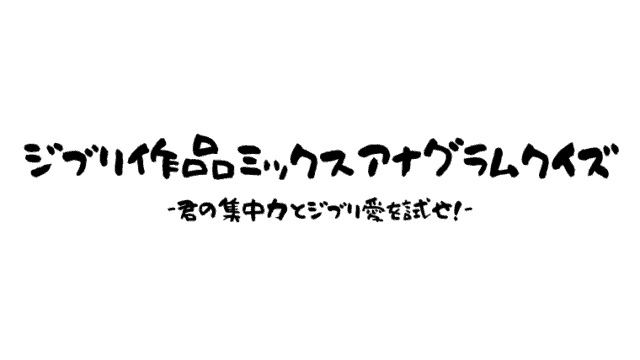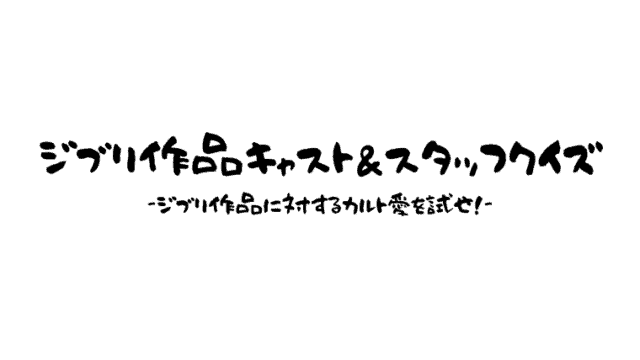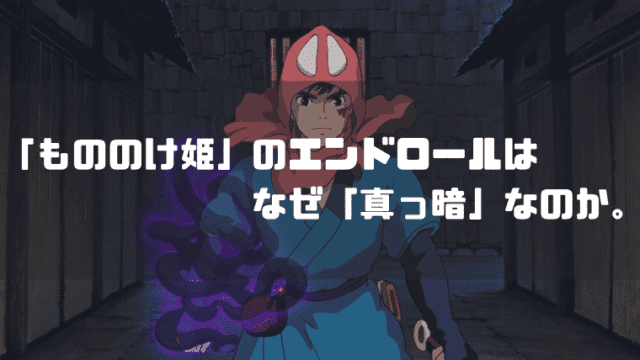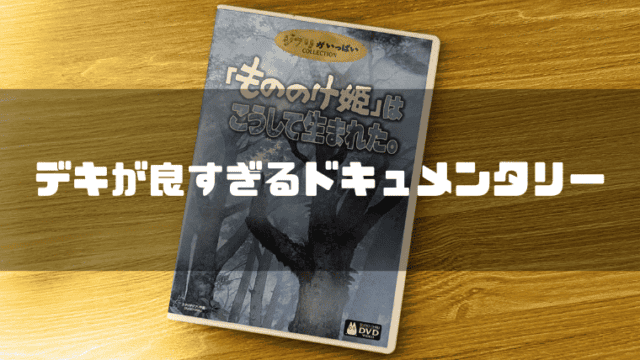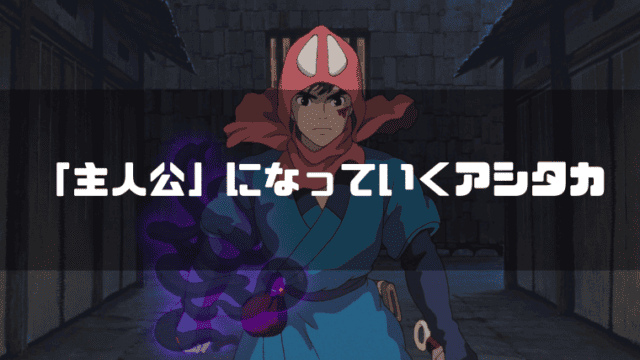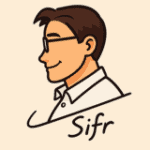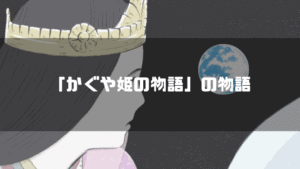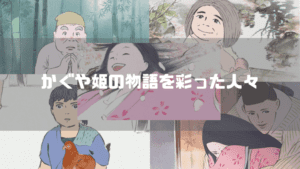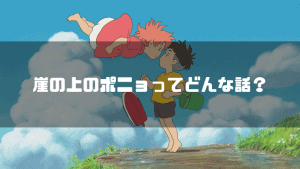「シンエヴァンゲリン劇場版:||」は2021年に公開された庵野秀明監督による劇場用アニメーションであり、TV版から始まるエヴァンゲリオンシリーズの完結編であった。
一方で「もののけ姫」は、1997年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーションであり、我々一般大衆にとっての「ジブリブランド」や「宮崎駿ブランド」を決定づけた作品であった。
今回は「シン・エヴァンゲリオン」という作品の見方の1つとして、エヴァンゲリオンがようやくたどり着いた「もののけ姫」だったのではないかという視点で色々語っていこうと思う。
実のところ「エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」についてはすでに以下の記事を書いたことがある。
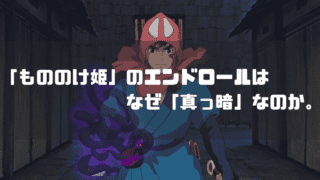
ただ、上の記事を書いたときにはまだ「シン・エヴァンゲリオン」は公開されていなかったし、どちらかというと「もののけ姫」よりだったので、「シン・エヴァンゲリオン」公開からそろそろ1年ということで、再び2作品の関連について書いていこうと思う。
以下の文章はネタバレに関してなんの気遣いもないものになりますので、その点はご了承ください。
- 「エヴァ」と「もののけ姫」の共通点は「傷ついた人々」
両作品とも、主人公を含む登場人物が深い苦悩や過去を抱えており、その中での生き方や関係性を描いている点で共通している。ネルフとタタラ場はそれぞれ「心に傷を持った者たちの居場所」として描かれる。 - 決定的な違いは「救いの有無」
「もののけ姫」ではアシタカがサンという存在と出会い、未来への希望を見出す一方、「旧劇」や「エヴァQ」までのエヴァは、シンジにとっての救いがなく、終始希望のない物語構造となっていた。 - 「シン・エヴァ」における真希波マリの役割
真希波マリは、シンジにとっての「サン」のような存在であり、彼を閉じたループから解放する福音として登場した。「マリと走り出すシーン」は、シンジの新たな人生の始まりを象徴している。 - 「第3村」と「タタラ場」の共通性
第3村の人々は苦しみを抱えながらも他者に思いやりを向け、前向きに生きているという点で、タタラ場の人々と共通している。彼らの姿が、シンジの再生と希望の鍵となっている。 - 緒方恵美の「さよなら」がエヴァの真の終幕
シン・エヴァのラストでは声優が神木隆之介に変わったが、「さよなら、すべてのエヴァンゲリオン」という緒方恵美のセリフこそが本当の終わりを示すものだったと解釈できる。エヴァの物語は緒方さんによって始まり、締めくくられたとも言える。
「エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」
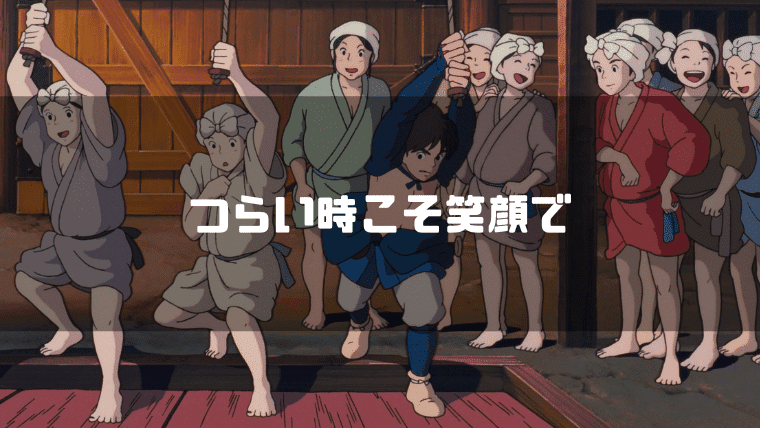
2作品の共通点
まずは「エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」の共通点について考えていこうと思う。まずは、シンジくんを筆頭とする「エヴァンゲリオン」の登場人物について思いを馳せよう。
シンジとネルフの面々
2作品の最も重要な共通点は「登場人物たちの苦しみ」ということになるだろう。
「エヴァンゲリオン」におけるシンジは、両親からの愛情を受けることなく成長し、どうしても自分の価値を見つけられずにいた。そしてようやくの再会を果たした父碇ゲンドウからは「シンジ、寂しい思いをさせて済まなかったな」の一言もなしに「エヴァに乗れ」という知能指数マイナス無限大のアホ命令を受けるという仕打ちを受ける。
そして状況はそれにとどまらず、生活をともにした葛城さんを筆頭に、シンジくんよりも年上のネルフの人々もまた、何かしらの心の傷や鬱屈した思いを抱えており、14歳の少年を最前線に送り出すことに対する後ろめたさや矛盾について考える余裕すらない(素振りくらいは見せたかもしれないが)。
というよりも、「使徒」という謎の驚異との戦いの渦中に自らを置くことによって、自分が抱えている問題から目を背けることができている状態にある。彼らは戦わなくては生きていけないし、シンジに同情する余裕は。ましてや心のケアなんてことは全然できない。
ある意味でネルフという組織は「傷ついたものの寄り合い所」だったのかもしれない。
ここに書いたネルフの面々のイメージは「エヴァQ」までの、シンジくん以外の登場人物に関するものである。「エヴァQ」に至るまでにただ1度だけ、シンジくんはとてつもなく前向になった。もちろん、TV版ラストのシンジくんである。考えれば考えるほどあれでキチンと終わっていたようにしか思えないのだが、あのときに俺たちがちゃんと納得していれば、みんな幸せでいられたのだなと、つくづく思う。
アシタカとタタラバの面々
一方「もののけ姫」のアシタカも、とんでもない苦境に叩き落される。
アシタカは故郷の集落を襲った「タタリ神」を駆逐したが、その結果として「呪い」を受けてしまう。そんな「呪い」を受けたアシタカだが、彼の功績は未来永劫讃えられるはずのものだった。
しかしそうはならなかった。いや、なったのかもしれないが、彼自身が集落で栄光の日々を送ることはなかった。
集落の人々は、なにやら「掟」に従って、英雄アシタカを集落から追放したのである。理由は彼が否応なしに食らった「呪い」である。そんな存在を集落においておくわけにはいかないという理屈であった。
彼は長老の示唆に従って、宛のない「西への旅」を続けるが、その先に彼の「呪い」が解決する保証などない。延々と続く宛のない旅だった。
そんな彼は最終的に「タタラバ」にたどり着く。たたら製鉄を生業とするその地に生きる人達は「タタラバ以外では生きることができない人々」であった。彼らは多くを語ることはなかったが、ネルフの面々と同一に心に傷を抱え、鬱屈した思いの中で生きている。彼らにとって「タタラバ」は最終到達地点であり、そこを失ったら行き場がないのである。
「タタラバ」で生きるということは生易しいことではなく、過酷なことだった。しかし、「タタラバ」以外での生活に比べればその過酷さは許容できるものであり、その「主体的な苦しみ」は、「タタラバ」の人々にとっての「使徒」だったのかもしれない。忙しさはいっとき、人を現実から開放してくれるのかもしれない。
2作品の相違点
このように「エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」は「苦しみの中にある人々」が登場しているという共通点があるが、その描かれ方に決定的な差がある。
「エヴァンゲリオン」はシンジくんを筆頭に、すべての登場人物が自らの苦しい思いを前提に、苦しいときに苦しい顔をして苦しいときに周りにあたり散らす。
一方で「もののけ姫」では、アシタカを筆頭に、すべての人が自分の苦しみをひた隠しにし、目の前の人に笑顔を見せる。
エボシ御前わずかにアシタカに苛つきを見せているのだが、彼女が食らった苦境を思えば、アシタカの日々に同情することができなかったとしても無理はないかもしれない。

そして、最も重要な違いは「アシタカはサンに出会えたが、シンジくんは「エヴァQ」に至っても「サン」に出会えなかった」ということだろう。
物語の「救い」はどこにあるのか?

「旧劇場版」への不満
我々が「エヴァンゲリオン」という物語から卒業できなかった理由の最たるものは「旧劇場版」のラスト「気持ち悪い」だろう。
実は「旧劇場版」の時点で、多くの謎は解かれている。少なくともゲンドウの思惑は分かったし「人類補完計画」で実現したかったことも明らかにはなっている。でも我々は「エヴァンゲリオン」という物語を消化した気になれなかった。
理由は1つ。
「それでもなお」現実を選んだシンジくんが全然救われているように思えなかったから。
やはり我々は「エヴァンゲリオン」を「シンジくんの物語」として見ているので、最後の最後に「気持ち悪い」と言われてしまうと「終わった!」という爽快感などあるはずもないのである。
物語の大団円のためには、シンジくんへの「救い」がどうしても必要だった。でもそれがなかった。これが「旧劇場版」までというか「旧劇場版」への不満だったのだと思う。
実のところTV版のラストではシンジくんはキチンと救われている。シンジくんは最後「ぼくはここにいてもいいんだ!」とようやく当然の事実に気づくことができている。あれで我々が納得すればよかったのだが、それができなかったら生まれてしまったのが「旧劇場版」なのだろう(庵野監督ごめんなさい)。
ただ結果的に、全く救いが無い物語になってしまったのが「旧劇場版」だった。TV版ではシンジくん結構頑張ってたのにね。
「もののけ姫」における「救い」-サンの存在-
なんとも救いの無い物語なってしまった「旧劇場版」に比べて「もののけ姫」にはサンという福音が存在していた。
実のところ「エヴァンゲリオン」も「もののけ姫」も、最終的に「解決策」を与えていない点では同じことになっている。それくらい当時の作り手にとって「世界」は苦しい存在にあったし、当時のリアリティとしては「解決策」などというものを提示できる状況にはなかったのだろうと思う(現代的にはお見事というしかないが、お見事でなかったほうが我々は幸せだったのだろう)。
それでもなお「もののけ姫」の主人公アシタカは、サンに出会う事ができた。
サンという存在を語り切ることは難しいことだとは思うが、アシタカにとっての「福音」であったことは間違いないだろう。
彼は「タタリ神」から受けた呪いを理由に故郷から追放され、その呪いを癒す方法があるかどうかも分からないままに西へ西へと孤独な旅を続けた。彼がジコ坊から聞き知った「シシ神」という存在は、絶望の淵にいる彼にとっての「蜘蛛の糸」であったに違いない。
しかし、皆様御存知の通り「シシ神」は彼の呪いを癒やしてはくれなかった。その絶望の事実を知った瞬間に、アシタカは自らの命運を受け入れ。それ以降の人生をサンに捧げることを決めた(と私は思っている)。
「もののけ姫」のラストでアシタカの「呪い」はわずかに薄まったが、結局残ってしまった。それは「解決不可能な問題の集合体としての社会」の象徴だったのだろう。それでも彼にとっては延命状態であり、サンという存在のためにその人生を使うことができることを意味していた。
サンの存在はアシタカにとってまさしく「福音」であったのだと思う。
「エヴァQ」までの「救い」のなさ
では「旧劇場版」まで、あるいは「エヴァQ」までのシンジくんはどうだっただろうか?
「旧劇場版」ではギリギリのラインで「それでもなお人と関わる世界」を望んだシンジだったが、アスカに「気持ち悪い」と言われる始末であったし、「エヴァQ」では結局絶望の旅路についてしまった。「旧劇場版」に比べてわずかにアスカが優しかったことが唯一の「救い」に見えなくもないが、基本的にシンジくんはアシタカのように目的地のない旅路に就くこととなった。
衝撃!真希波マリ
「エヴァQ」までは特段「救い」や「福音」を与えてくれなかった「エヴァンゲリオン」だったが、皆様御存知の通り、「シン・エヴァンゲリオン」にはまさに「救い」「福音」があった。
それこそまさに真希波マリである。
「新劇場版」で突如登場した「真希波マリ」に困惑したのは私だけではないだろう。結局「シン・エヴァンゲリオン」が完成するまでなぜ「真希波マリ」が必要だったのか全くわからなかった。そして、「もののけ姫」との比較をするならば、「真希波マリ」はシンジくんにとっての「サン」だったのだということが分かるだろう。
アシタカの宛のない西への旅を終わらせたものは「サン」というこれまでの人生に存在しなかった外的な存在であったように、「エヴァンゲリオン」という呪いの旅からシンジくんが開放されるためにはこれまでにない外的な存在が必要になる。そうでなければ同じことを延々と繰り返すことになったのだろう。「エヴァQ」までの様々な考察の中に「ループ」があったのは今となっては当然のことだったと思えるが、その「ループ」を打ち破り、シンジくんにとっての「新しいなにか」を見つける鍵が「真希波マリ」だった。
「シン・エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」
シンジくんやアシタカの苦難は「自分ではどうすることもできない、自分のせいではない何か」の象徴であっただろうし、それは「もののけ姫」や「エヴァンゲリオン」という物語に通底する本質的なテーマであったと思われる。
しかし、「エヴァQ」までと「もののけ姫」を比較するとその結末は決定的に異なっていた。
アシタカは「サン」という存在を発見することによって、それでもなお新しい未来へと歩みを進めた。
一方で「エヴァQ」までは「そんな苦しみどうしようもない」という状況にとどまっていた。
「シン・エヴァンゲリオン」のラスト、マリとシンジが走り出すシーンは、シンジくんがようやく「それでもなお新しい未来」へと走り出したシーンであろう。別にその先にキラキラした未来だけがあるわけではない。これまでになかった様々な苦難にさいなまれることになるのだろう。
しかし、シンジとマリは新たな一歩を歩みだした。
「シン・エヴァンゲリオン」は2021年になってようやく到達した「もののけ姫」の境地だったのではないだろうか。
「タタラ場」としての「第3村」
「シンジとマリ」「アシタカとサン」という対比も重要なのだが、もしかしたらより重要な観点となるのが「第3村」だろう。
あの「第3村」は「第3新東京市」のやり直しに見える。あるいは「シンジくんを囲む世界」のやり直しかもしれない。そして「第3村」は「タタラ場」に違いない。
「第3新東京市」や「ネルフ」の面々を一言でまとめるならば「自分のことで手一杯で、他人のことなんか気にしている暇がない面々」ということになるだろう。
一方で「タタラ場」で暮らす人々は「自分たちのことで手一杯なのに、目の前の人に笑顔を見せる面々」であった。アシタカが訪れた「ふいご」を踏む現場の人々はまさにそうだった。もちろん「タタラ場」の人々は、そこでの暮らし以前により苦しい状況にあった。でも、だからといって、「タタラ場」での生活が楽なわけではない。それでもなおあの人達はアシタカに「笑顔」を見せるのである。
「第3村」の面々もそうだった。原因を探ればシンジくんのせいで「第3村」の人々は苦しい生活を強いられている。それでもなお懸命に生き、他者に苦しい顔を見せず、前向きに日々を生るのが「第3村」だった。
あの人々の生き方そのものがシンジくんにとっての見本であり、「何度でもやり直す」というラストに繋がったのではなかっただろうか。
以上のように、「アシタカとサン」「シンジとマリ」「タタラ場と第3村」という対比で考えると「シン・エヴァンゲリオン」はようやく「エヴァンゲリオン」が到達した「もののけ姫」だったように、私には思えるのである。
作家にとっての「結婚」
さて、最後に残る問題は、なぜ「エヴァンゲリオン」は「シン・エヴァンゲリオン」という完結を得ることができたのか。別の言い方をするならば、なぜシンジはマリに出会えたのであろうか?
ない頭をフル回転するならば、やはり安野モヨコさんとの結婚しかないように思われる。
「もののけ姫」を作った宮崎駿監督も、「エヴァンゲリオン」を作った庵野秀明監督も、90年代後半という時代に同じものを捉えてはいたのだろう。少々穿った見方をするならば「エヴァンゲリオン」によってそういう時代であることに宮崎監督が気づいたのかもしれない。
しかし、両監督が描いた物語の顛末はあまりにも違った。それはやはり「結婚」が大きかったのではないだろうか。
すでに結婚もし、子供もいい大人になっていた宮崎監督は「サンはいるんだ!」という作品を作れた。
一方で、別にもてないわけでもないのに「結婚」あるいは「生涯のパートナー」という事実を手にしていない庵野監督の結論は「気持ち悪い」になってしまったのかもしれない。
庵野監督も「結婚」という喜びを得たことによって「もののけ姫」における「サン」と同じように「真希波マリ」を登場させることができるようになったのかもしれない。
もちろん庵野監督の内面なんてわからないし、ここに書いていることはおそらく間違っているのだろう。でもそんなふうに思えてしまうのである。
嗚呼、けっこんして~
ありおりはべりいまそかり
おまけ:さようなら、すべてのエヴァンゲリオン

「シン・エヴァンゲリオン」を語る上で無視できないのは、ラストシーンでのシンジくんの声優が神木隆之介であるという事実だろう。
作品の消費者である我々としてはむしろ納得のいく状況であり、「あっ、状況が変わったんだ、エヴァンゲリオンは終わるんだ!」と思える演出であった。
しかし、TV版からずっとシンジくんの声優であった緒方恵美さんの心情はどのようなものであっただろうか。
なぜ、ずっと碇シンジを演じてきた自分の声が、「エヴァンゲリオン」という作品のラストボイスではないのか。それくらいの疑問(あるいは不満)は持ったのではなかろうか。
「シン・エヴァンゲリオン」の制作ドキュメンタリーや緒方さんの発言を見ても、どうも煮え切らないものを抱えていたように思われる。
『シン・エヴァ』緒方恵美、「終われていない」碇シンジ役 14歳を演じ続けた“痛み”
緒方さん最後の名演は「さようなら、すべてのエヴァンゲリオン」というセリフだった。
それは「シン・エヴァンゲリオン」は「我々がエヴァンゲリオンとさよならをするための物語」であることを露骨に表現するセリフであったものの、形式的にはラストのセリフではなかった。
やはり「エヴァンゲリオン」を締めくくるセリフは緒方さんのものであってほしかったという思いもあるし、そうであるべきだったという思いもある。そう考えると我々としても不満は残るのだが、考えようによっては「エヴァンゲリオン」を締めくくったのは緒方さんの「さよなら、すべてのエヴァンゲリオン」だったと考えられなくもない。
つまり、「さよなら、すべてのエヴァンゲリオン」というセリフを持ってして「新世紀エヴァンゲリオン」という物語は終焉したのだと考えればよいのである。そのように考えれば、緒方さんのセリフは「エヴァンゲリオンのラスト」と位置づけることができる。
あのセリフのあとは「エヴァンゲリオン」のない、まったく別の世界になっているのだから、その世界にいる「シンジ」の声を緒方さんが担当するのはむしろ間違っていると言えなくもない。
このように考えれば、我々にとっての「エヴァンゲリオン」は「緒方さんに始まり緒方さんによって終わった」と考えることができるのではないだろうか。緒方さんご自身がどう感じておられるかは私にはわからないが。
おわり。
P.S.
庵野秀明監督以外の人間にとっては「さよならした」ではなく「さよならさせられた」というのが正しい表現となるきがするので、この辺のことも緒方さんの何やら煮え切らない状況に影響したのかもしれない。
ほんとにおわり。
この記事を書いた人
最新記事
- 2025年4月15日
【シン・仮面ライダー】オーグメントの絶望の謎と「アイ」が隠した本当の戦略-本郷猛は何故勝利して良いのか- - 2025年3月25日
【侍タイムスリッパー】あらすじとその考察-椿三十郎の呪を打ち破る「究極の殺陣」- - 2025年3月2日
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」を見た感想と考察ーテム・レイの正しさとレビル将軍の行方ー - 2025年2月26日
「機動戦士ガンダム」スペースノイドの怒りと地球連邦政府という奇跡ー物語を支える3つの重要な側面を考察ー - 2025年2月9日
【ベター・コール・ソウル】ジミー・マッギルの不可思議な人間性を考察-ソウル・グッドマンとは何だったのか-