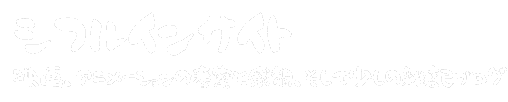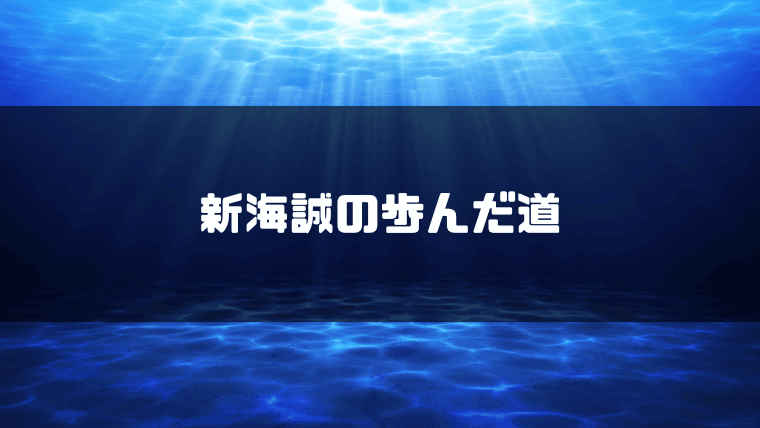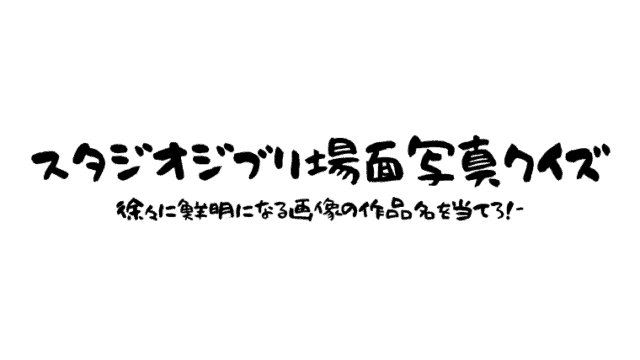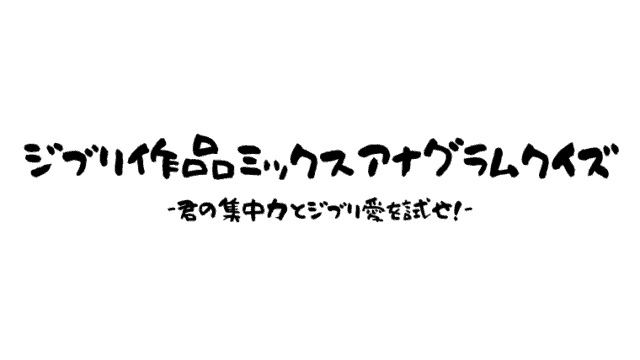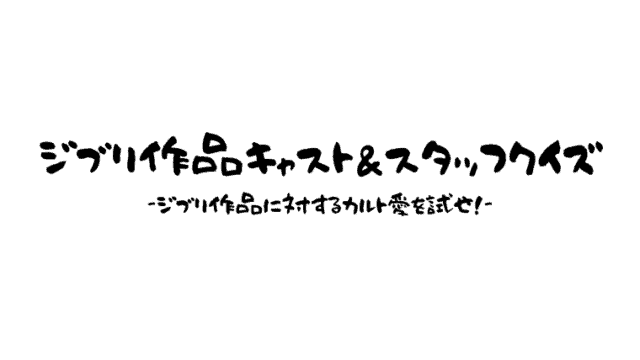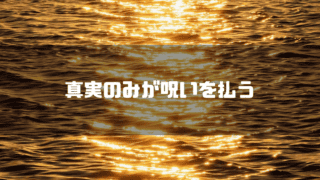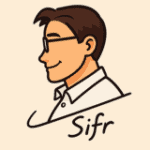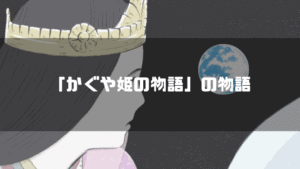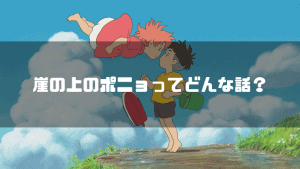新海誠監督は日本のアニメーション映画監督である。主な作品として、
- 「ほしのこえ」(2002年)
- 「雲のむこう、約束の場所」(2004年)
- 「秒速5センチメートル」(2007年)
- 「星を追う子ども」(2011年)
- 「言の葉の庭」(2013年)
- 「君の名は」(2016年)
- 「天気の子」(2019年)
- 「すずめの戸締まり」(2022年)
を発表している。
私が初めてみた新海作品は「雲のむこう、約束の場所」だったが、それ以降新海作品が好きで何度も見ている。
今回は、数が増えてきた新海作品を全体的に見たときのそれぞれの作品が持つ立ち位置を自分なりにまとめていこうと思う。
それぞれの作品はまったく異なるが、通底するものを感じさせ、同時に変化も見られる。新海誠監督作品はどのような変遷を辿ってきたのだろうか。
-
新海誠作品における人間関係のテーマの変遷
新海監督の作品は、「会いたくても会えない」「喪失と再会」「人と人の繋がり」など、時代とともに変化する人間関係を描いてきた。初期は距離や喪失を強調する作品が多く、「君の名は」以降は再会や希望へとテーマがシフトしている。 -
新海作品の方法論の変遷
作品の舞台設定も変遷を遂げており、初期はSF要素が強かったが、「秒速5センチメートル」や「言の葉の庭」ではリアルな世界観を描き、「君の名は」以降はファンタジー要素を取り入れた大衆向けの作品へと移行した。「星を追う子ども」はこの変化の分岐点となる作品と考えられる。 -
新海作品の結末の系譜と「こうであるべき期」
初期作品は「こうである(現実の厳しさ)」を描いていたが、「君の名は」以降は「こうであるべき(希望や未来への選択)」が強調されるようになった。「天気の子」は個人の選択が世界に影響を与えるというメッセージを持ち、「すずめの戸締まり」では親子関係を通じて成長や対話の重要性が描かれている。
新海誠監督作品の変遷と系譜

人間関係についてのテーマ性の変遷
まずはこれまでの新海作品の「人間関係に関するテーマ性」を一言でまとめることから始めてみると;
- 「ほしのこえ」⇒繋がっているのに会えない
- 「雲のむこう、約束の場所」⇒もう君は居ない
- 「秒速5センチメートル」⇒会いたいのは私だけ
- 「星を追う子ども」⇒あの人にもう一度会いたい
- 「言の葉の庭」⇒私はここにいる
- 「君の名は」⇒二度と君を忘れない
- 「天気の子」⇒君に会いに行く
- 「すずめの戸締まり」⇒会いたい人は会った人
大体こんなものだろうか(もちろん異論はみとめる)。それぞれについて、もう少し詳しく述べていこうと思う。
「ほしのこえ」
これは特に説明する必要はないのだが、「携帯メール」という形でつながっているのにもかかわらず会えない切なさが見事に描かれていたので「繋がっているのに会えない」とした。
現代的に見ると「ガラケー」であることがむしろいい味になっていて、その切なさが強調されているように思われる。
「雲のむこう、約束の場所」
一言にまとめるうえで一番むずかしかったのは「雲のむこう、約束の場所」であった。「もう君は居ない」というと誰かが死んでしまっているような印象を受けるのだが「大切な記憶を失う」ということによって浩紀が佐由理を失ったという意味で「もう君は居ない」とした。
「秒速5センチメートル」
この作品については貴樹の一方通行感を強調して「会いたいのは私だけ」としたが、「秒速5センチメートル」の結末を見ればそんな身も蓋もない物語になっているわけではない。
彼はフリーランスとして見事に成功を収めている。
ただ、会社を辞める前に付き合っていた 水野理紗 や高校の時の同級生 澄田花苗 のことを思えば「会いたいのは私だけ」であっていると思う。
「星を追う子ども」
「星を追う子ども」の主人公は間違いなく明日菜であるが、物語を推進しているのは森崎竜司である。
「新世紀エヴァンゲリオン」の碇ゲンドウほどではなかったが、竜司の執着たるや並大抵のものではなかった。彼は亡き妻に再会するためにすべてを利用した。最終的には主人公である明日菜おも(この辺にはなにか倒錯的なものも感じたね)。
一方主人公の明日菜も、明確にその意思を表明してはいないのだが、失われた「父」なる存在の喪失を埋めるように「ここではない何処か」へと通信を試みていた。
主人公のほうが達観しているように見えるものの、森崎竜司という極端な存在がわかりやすく明日菜の内面を代表していてくれたとも見ることもできる。そういう意味で「あの人にもう一度会いたい」とした。
「言の葉の庭」
「言の葉の庭」を一言にまとめるのも難しかったが、ドロップアウトしている(しかけている)ユキノ先生がそれでも「そこ」にいること、そして、主人公である孝雄が「俺はここにいるのに!」と暗に訴え続けていたことを持って「私はここにいる」とした。
ただ、物語の構造と顛末を見ると「ここではない何処かへ」みたいなことも考えられるが、個人的には「私はここにいる」を採用したかった。
君の名は
これは特に迷うことはなかった。「言の葉の庭」まで作品を作ってきた新海監督が「こうである」から「こうであるべき」へと明確に物語の作り方を変えた作品だと思う。
「君の名は」は間違いなく忘却の物語であり、失敗の物語である。隕石の衝突という大切な現象を伝えそこねたのだから。
そしてその忘却と失敗を我々の社会のそれと重ねつつ、最終的に滝と三葉は再会を果たす。
それはつまり「我々は忘れるものだし忘れてしまったのだけれども、『彼ら』はきっと忘れない」という未来への期待と希望をラストに乗せたということだろう。
この作品から明確に「私小説感」はいい意味でなくなった。
ただ、映画が監督の私小説であるという構造は映画が持っている根本構造だと思うので、それは決して失われていないと思う。
「天気の子」
大ヒットだった「君の名は」の次の作品として多くの期待の中で公開された作品だったと記憶している。
作品そのものが持っているテーマ性としては「私達がやりました」とか「ここではない何処かへ」でいいと思うのだが、あえて「人間関係」ということにすると「君に会いに行く」で良いと思う。
物語のラストで帆高は所在のない気持ちの中で再び東京に赴くが、その目的は陽菜である。「言の葉の庭」にも「君に会いに行く」という要素はあると思われるが、物理的な距離の差を鑑みて、帆高の積極的な行動をその本質と捉えて「君に会いに行く」とした。
「すずめの戸締まり」
「君の名は」から続く三部作の最終章であった本作。主人公の鈴芽は九州から東北までを移動し、様々な人と出会う。
その出会いがロードムービーとしての「すずめの戸締まり」を彩るのだが、東北で物語が完結し、そこから再び吸収に戻る光景がエンドロールで描かれる。そこで描かれた「再会」こそがこの映画の本質であったように思える。
様々なギミックを駆使して描かれた物語だったが、「人の行く道は多くに人に支えられている」という極めて素朴なことを描いてもいる。
そしてエンドロールで九州に帰るその旅路が描かれ、鈴芽たちはその人達と再会を果たし、母親として鈴芽を育て上げた環と共に挨拶周りをする。
あの姿こそがこの映画の本質であるような気がするので、この作品の一言まとめは「会いたい人は会った人」とした。
新海作品の持つ方法論の変遷
映画は基本的に人間ドラマなのでその関係のテーマ性はとても重要だが、それをどのような舞台で描いたかも重要だろう。
これについては以下のようにまとめることができる:
- 「ほしのこえ」⇒SF
- 「雲のむこう、約束の場所」⇒SF
- 「秒速5センチメートル」⇒リアル路線
- 「星を追う子ども」⇒ファンタジー
- 「言の葉の庭」⇒リアル路線
- 「君の名は」⇒ファンタジー
- 「天気の子」⇒ファンタジー
- 「すずめの戸締まり」⇒ファンタジー
個人的に未だに理解が及んでいないのは「言の葉の庭」というリアル路線の物語が「星を追う子ども」と「君の名は」の間にあった事実である。
新海監督としてはある種の必然があってこのような流れになったのだと思うのだが、今のところ仮説も立たない。
結局のところ「星を追う子ども」が新海作品の系譜の中でどのような意味を持っていたかを言葉にできなければ、この謎を解くことはできない。
実は過去に「星を追う子ども」について記事を書いたことはあるのだが、結局自分自身の疑問に答えるものではなかった:

皆さんにとって「星を追う子ども」はどのような作品に見えただろうか。個人的には極めて重要な作品だと思っている。
新海作品の結末の系譜と相互関係
ここからは新海作品の「結末」に関して考えていこうと思う。
私もそうだったが、新海作品の結末に関して決定的に「おやっ?」と思ったのは「君の名は」のラストではないだろうか?
「君の名は」のラスト付近で滝と三葉は歩道橋で邂逅を果たすが、それに気が付かない。私はそれで物語が終わると思ったが、映画はもう少しだけ続き、最終的に二人は再会を果たした。
みんな歩道橋で終わっちゃうと思ったよね?
このように新海作品はどこかのタイミングでその結末のあり方に変化があったということになる。ここではその差を「(世界は)こうである期」と「(世界は)こうであるべき期(こうであってほしい期)」として分けて分類してみようと思う。
そうすると・・・
「ほしのこえ」「雲のむこう、約束の場所」、「秒速5センチメートル」
「君の名は」「天気の子」「すずめの戸締まり」
そして残りは・・・
「ほしを追う子ども」「言の葉の庭」
というグレーゾーン期ということでどうだろうか。
こうである期について
一番わかりやすいのは「こうである期」だろう。
「ほしのこえ」は近未来を描くことによって、現実社会において近くにいる人が感じる距離を本当の物理的距離として描いた(きちんと相対性理論が効いているのでSF)。
「雲のむこう、約束の場所」はこの世界に対して自分が何も寄与していないという絶望を描いている。
「雲のむこう、約束の場所」がそのような物語であることに異議がある人もあると思うが、私の考えは以下の記事にまとめている:

「秒速5センチメートル」は二重に「こうである」が描かれていることに特徴がある。一つは「恋愛」という観点における「こうである」。そしてもう一つは「人生」における「こうである」。
主人公の貴樹は初恋が実らなかったという点において「こうである」を生きているのだが、それと同時に、最終的にフリーランスとして生きるとう選択をしている点において新海誠的「こうであった」になっている。
新海監督はそのような人生を歩んだ人であった。
つまり、「秒速5センチメートル」までは「こうである」という話になっていた。
こうであるべき期について
「こうであるべき期」の最初を飾ったのは「君の名は」であった。ただ、この「こうであるべき」というのは単純に前向きなエンディングということではない。
前向きであるのは「秒速5センチメートル」から続いている。「星を追う子ども」では死別を乗り越えているし、「言の葉の庭」で主人公はラストで本音を絶叫し、ユキちゃん先生は新天地で新たな一歩を踏み出している。
ではそれまでの作品と「君の名は」の何が違ったのかというと、あのラストはつまるところこっ恥ずかしかったのである。
「君の名は」は「恋愛」という観点でなんとも美しいラストを遂げてくれた。
単に前向きなラストということならそれまでも合ったのだが、恋愛という観点でみるとそういった作品はこれまでなかった。
その不可能性こそが新海作品にあったある種の安全圏だったのだけれど、それを飛び越えてくれたわけである。
ただ、あのラストは「恋愛の成就」という側面以外にも「こうであるべき」を描いているとは思うが、それについては以下の記事にまとめている:

では「天気の子」はどうであったか?
私が考えるところでは、「天気の子」が飛び越えてくれたのは「雲のむこう、約束の場所」である。
「天気の子」で主人公 帆高は愛するものを救うために世界を犠牲にするというなんとも世界系的な判断を下し、結果的に雨がやまない世界を生み出してしまった。
ところが、帆高は物語のラストで「浮遊」してしまう。あれは確かに自分がしでかしたことであるのに、実際のところ皆あまり困っていないし、須賀には「そんなわけないだろ」と自分がしでかしたという事実をも否定されてしまう(あれは須賀のやさしさであったが)。
あの「浮遊」は、「雲のむこう、約束の場所」の主人公 藤沢浩紀が映画のラストシーンの後で感じていた違和感であっただろう。自分はあの塔を破壊したのに、世界は自分とは関係なく当たり前のように過ぎてゆく。しかも沢渡佐由理はその大事件を目撃していないし、大切な思いを忘れている。
一方で「天気の子」のラストで帆高と陽菜は「私達はだいじょうぶだ」と状況を肯定する。
二作品を比較すると、「雲のむこう」の頃は「それでも世界はまわる」というある種の達観が描かれているが、「天気の子」では「世界をまわしているのは君たちなんだ!」という新海監督のメッセージが強烈に描かれている。
多くの作品を作った新海監督が、藤沢浩紀にかけたかった言葉かもしれない。
いずれにせよ「天気の子」で描かれた「こうであるべき」は「自分が世界をまわしているという自覚をもつべき(もってほしい)」ということになるだろう。
そして「すずめの戸締まり」
この作品で描かれた「そうであるべき」は何だったのか?
それはこの作品のハイライトに見出すべきだと思うのだが、個人的なハイライトはやはり環(たまき)の絶叫シーンだと思う。
あのシーンを色々言語化することはできるとは思うが、そこで描かれたことを端的にまとめると「一生に一度は親子喧嘩を」になると思う。
親子の対立は極めて深刻なものとして捉えられるし、当事者にとっては本当に深刻なものなのだけれど、あってはならないものではない。むしろあるべきものかもしれない。
何より、すでに結婚し子どもがいた新海監督にとっては避けて通れないトピックスだったとも言えるのではないだろうか。
以上が現状私の考える新海作品の系譜と相互の関係である。相互関係についてはあまり深く考えることができていないが、今後色々と加筆されていくことになると思う。
以上。
この記事を書いた人
最新記事