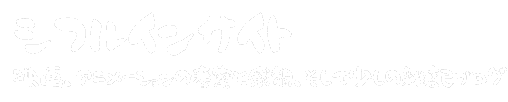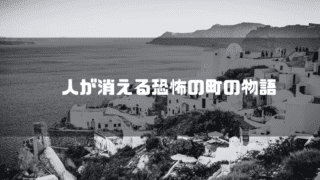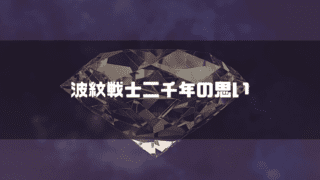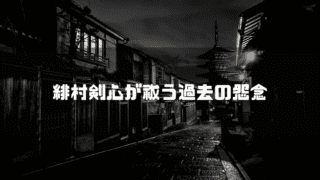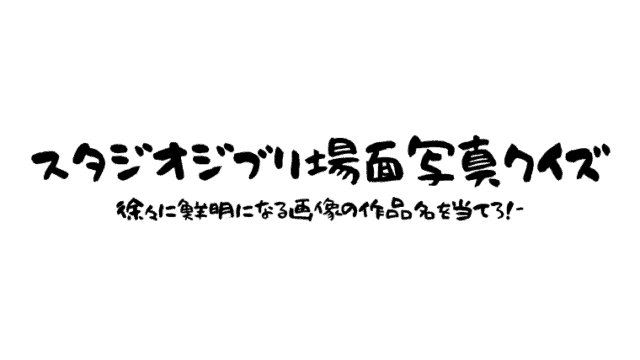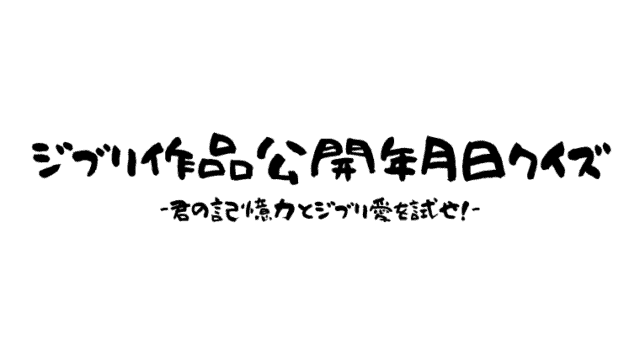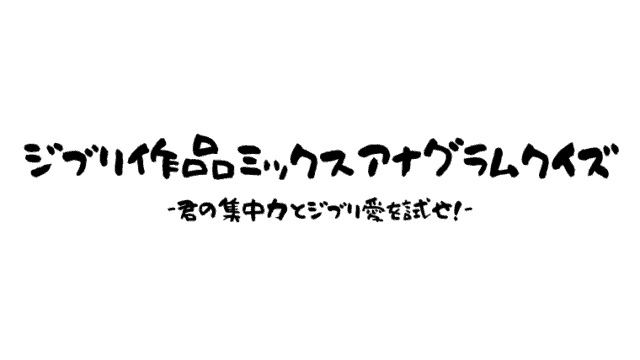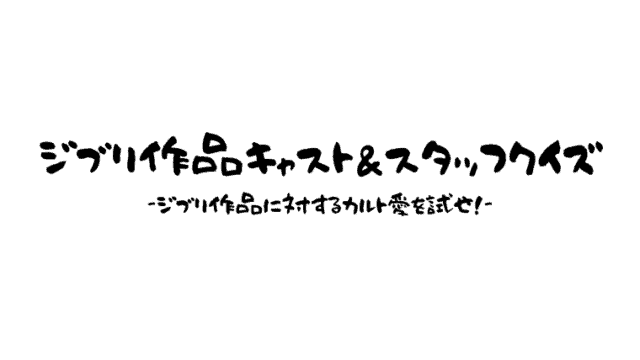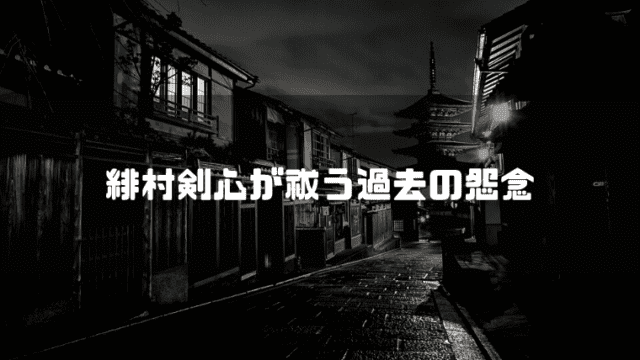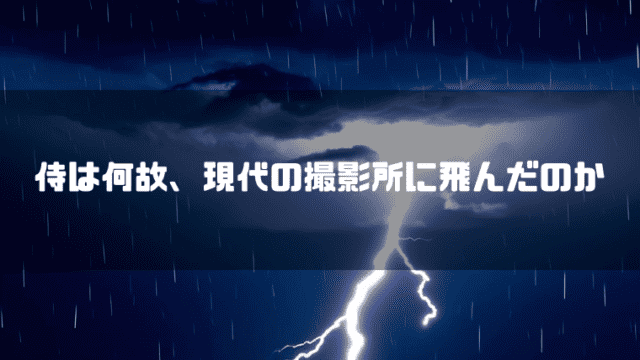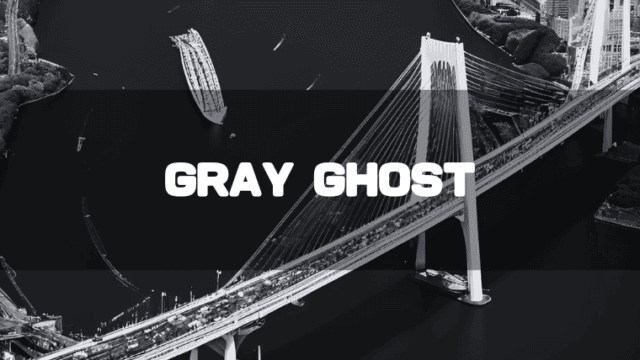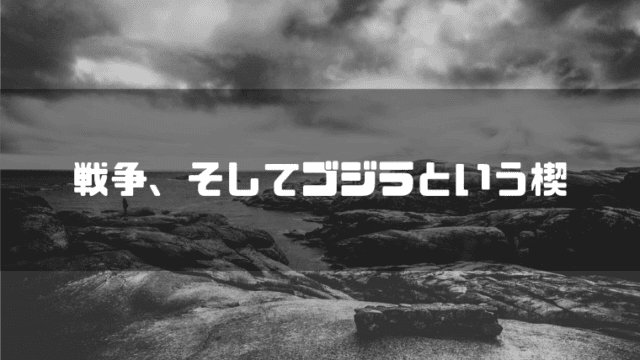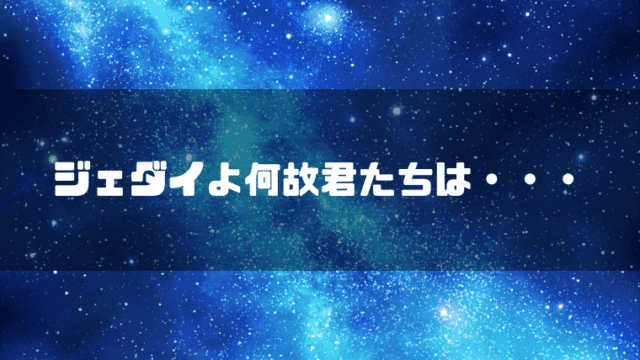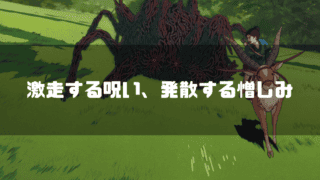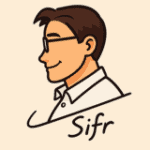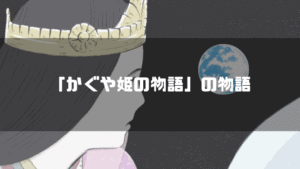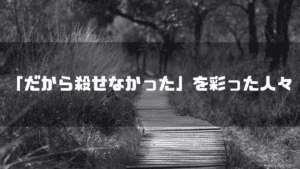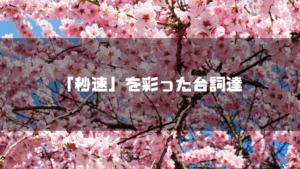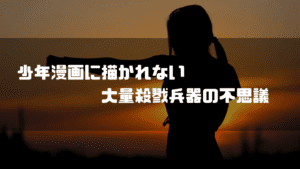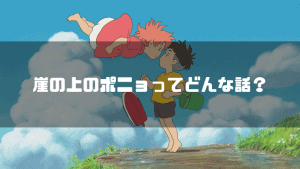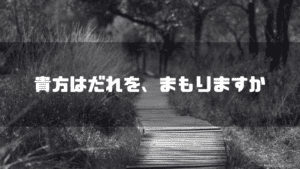映画「岸辺露伴ルーヴルへ行く」は2023年5月26日に公開された、高橋一生主演、渡辺一貴監督による劇場公開作品である。原作は2009年に発売された荒木飛呂彦による同名漫画作品である。
原作は「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフである「岸辺露伴は動かないシリーズ」の一部であるが、もはやスピンオフというよりは「ジョジョシリーズ」と同列のライフワークと言えるのではないだろうか。テレビドラマシリーズも、主人公の漫画家岸辺露伴を高橋一生、渡辺一貴演出で2020年からNHKで放送されており、個人的にとても気に入っている(漫画もドラマも)。
今回は映画「岸辺露伴ルーヴルへ行く」について語っていこうと思う。特に、物語の重要人物「奈々瀬」はなぜ岸辺露伴の眼の前に現れたのかということを考えたい。
もちろん映画がとてもわかりやすく作られているので、その理由を表面上考えることはできるのだが、映画を見る醍醐味はそれをこねくり回すことにある。今回はそういうことをやっていこうと思うし、このブログでは基本的にそういうことをしている。その上で「岸辺露伴ルーヴルへ行く」という作品の面白さを見ていきたい。
- 奈々瀬が露伴の前に現れた理由
奈々瀬は呪いの絵に囚われた存在として、絵の「血筋」にあたる岸辺露伴の前に「何かを伝えるため」に現れた。若き露伴が仁左衛門に似ていたことも、奈々瀬を引き寄せた要因の一つである。 - 「後悔」が現れる構造と奈々瀬の思い
絵は見る者の「血筋」に宿る「後悔」を顕在化させる力を持ち、露伴が襲われたのも奈々瀬の深い後悔によるものだった。幽霊は口下手だが、その感情を露伴がくみ取り、思いを遂げるのが物語の構造となっている。 - 露伴の主観としての物語と「願望の具現化」
奈々瀬や仁左衛門の姿は、実は露伴自身の願望や幻想によって作られた可能性がある。御神木の樹液がドラッグ的な作用を持つと考えれば、露伴が見た「幻覚」は願望の具現化にすぎず、物語全体が主観的世界だったとも言える。 - 物語の二面性が生む怪談としての面白さ
本作は「奈々瀬の願いを遂げる幽霊譚」であると同時に、「岸辺露伴の内面と倒錯した願望」が編んだ主観的物語でもある。その二面性の狭間にこそ怪談としての魅力があり、作品の奥行きと面白さを生んでいる。
「岸辺露伴ルーヴルへ行く」奈々瀬はなぜ、岸辺露伴の前に現れたのか?

まずは素直に考えてみる。
丁寧に作られている本編を素直に見ることによって、奈々瀬が岸辺露伴の前に現れた理由を考えると、それは主に3つ考えられる:
- 岸辺露伴の祖母の下宿(かつての旅館)で実質的に封印状態にあった仁左衛門の遺作が表に出てきた。
- 夫である仁左衛門の遺作に自らも囚われていた奈々瀬は「血族」である露伴やその祖母の前に現われ「なにか」を伝えに来た。
- 特に露伴の前に現れたのはその若さゆえ純粋さもあるが、夫の仁左衛門にそっくりだったから。
ということになると思う。この構造は日本古来からの怪談そのものの構造というか、なぜ幽霊が我々の前に現れてくれるのかということの説明になっている。つまり、幽霊は我々になにか大事なことを伝えるために現れてくれるのである。
ただ古来より、幽霊は口下手である。コレコレこういう理由があるので、こういうことをしてほしいとはどうしても言ってくれない。それを考え幽霊の思いに応えるのは我々生きているものの役割である。これはジョジョ第四部で岸辺露伴が語っていたことでもある(杉本鈴美の思いに応えきった露伴ちゃんは偉い!)。
意味ありげで、口下手で、それでいて激情的な奈々瀬の存在は、若き岸辺露伴にとっては「忘れがたき日」となったのだが、幾年経った後、これまた第四部と同様に岸辺露伴その思いに応える旅に出たのである。そして今回もその思いを実現した。
岸辺露伴は死人(しびと)の思いを遂げる天才である。
わずかに難しかった点
映画「岸辺露伴ルーヴルへ行く」は基本的にはわかりやすく作られており、発生したことの理由が少なくとも神秘的なレベルでわかるようになっている。
ただ一方で、少々難しかった点もあり、映画を見たあと、家に帰ってようやくわかったこともあった。
それは、岸辺露伴がその人生に全く干渉しなかった仁左衛門になぜか襲われているという現象である。
一応ヒントも描かれており、どうやら仁左衛門の絵は「血筋」をも遡ってその「後悔」を見せるらしく、本編でもエマの上司であったジャックが甲冑の戦士に切られている。
つまり、その血脈にある誰かの「後悔」が露伴の目の前に「殺意」として現れたということになる。つまり、その「後悔」をした人は、仁左衛門に殺されてもしょうがないと思っていたということになる。
もちろんそれは奈々瀬であり、自分が御神木の樹液を発見してしまったことを酷く「後悔」していたのである。その「後悔」が血筋を超えて露伴の「幻覚」して現れたということになる。
映画館で見ていたときにはこの構造は分からなかった。
露伴はなぜ最期に「後悔」を見たのか?
ただ、表面的に映画を見ているだけではどうしても説明がつかないこともあると思う。
例えば、一番最初に仁左衛門の絵に気がついたのが岸辺露伴であるにもかかわらず、「後悔」に囚われたのが一番最後だったということである。
登場人物の位置関係を見てもどうにもおかしいのである。なぜあんなことが起こったのか?
ここ以降は、少々私の想像の翼が羽ばたき始めます。
御神木の樹液はドラッグ
Z-13倉庫で岸辺露伴が最期に「後悔」に囚われた理由を無理くり考えると、ひとつの候補として挙げられるのは「御神木の樹液はドラッグだった」ということになると思う。
つまり、若き日の岸辺露伴の見た「夏の夢」は、仁左衛門の描いた絵の影響による幻覚であったが、仁左衛門の絵が密閉された状態にあったために、その影響が最小限におさえられ、若き岸辺露伴の「願い」が具現化したということである(「美しい女性」を描きたいという願いが具現化した)。
一方で、岸辺露伴はその頃にその「ドラッグ」にあてられていたので、Z-13倉庫で再びその絵にあったときにすでに耐性があり、最期まで「幻覚」を見なかった。
御神木が御神木であった理由は、その樹液で狂ってしまう人々が多かったからということになるだろう。少々突飛ではあるが、このような考え方もひとつあると思う。
奈々瀬出現を再考–岸辺露伴の主観としての物語–
「ドラッグ」という視点に立つと、奈々瀬が岸辺露伴の前に現れた理由は異なってくる。そもそも若き日に現れたのが本人の「願い」を具現化したものと考えるなら、Z-13倉庫で出会った奈々瀬も岸辺露伴の願いだったと考えるほかなくなる。
つまり、周りの状況と「モリス・ルグラン」が残した言葉によって、仁左衛門の絵が人の「後悔」を具現化するらしいと考えてしまった岸辺露伴は、その絵を見たら自分も「後悔」に出会うはずだと考えた。そして、岸辺露伴が誰よりも会いたかった「後悔」が奈々瀬であったので、その場に奈々瀬が現れたのである。そこに仁左衛門が現れたことも「岸辺露伴が会いたかった」で説明がつくし、襲ってきた理由は「みんながそうだったから」ということにできる。ある種の「集団催眠」の結果という言い方ができるだろう。
このように考えると、物語のラストですでに死人(しびと)であるはずの奈々瀬にヘブンズドアーをかけられたことも理由がつく。
あのとき岸辺露伴はすでに物語を編んでいたのである。
我々が事実と感じた仁左衛門と奈々瀬の日々は、本当にあったものかどうかわからない。あれこそが岸辺露伴が描いた願い(フィクション)であったのかもしれないのである。仁左衛門の顔が岸辺露伴と一緒(同じ俳優が演じている)という事実は、その願望の露骨な現れだった。そのように思える。
つまり、この立場に立つと、「ドラッグ」によって見てしまった「奈々瀬」という願望に、「奈々瀬の過去」という願望までのっけていることになるのでもはや倒錯である。でも、それでいいと思う。
「岸辺露伴ルーヴルへ行く」はそのような物語だった。
まとめ「岸辺露伴ルーヴルへ行く」の面白さ–狭間の物語としての怪談–
以上書いてきたことをまとめた上で、この映画の面白さを述べるなら以下のようになるだろう:
この映画は、「呪いの絵のモデル」になってしまった奈々瀬の「この絵をなくしてほしい」という願いがその根本にある物語として描かれている。物語のラストで判明するように奈々瀬の血族であった岸辺露伴は、その思いを完遂し、絵を葬ることに成功した。
この物語がそのような「幽霊譚」として描かれている一方で、実のところ「岸辺露伴の主観の物語」としても進行している。
「あの夏の日」に見た奈々瀬はそもそも岸辺露伴の願望でしかなかったかもしれないし、彼が見た伊左衛門も彼の「会いたい」という願望の現れに過ぎなかったかもしれない。伊左衛門と奈々瀬が関係していることも願望であれば、伊左衛門が自分に似ていることも願望ということもできる。
「岸辺露伴ルーヴルへ行く」はこういった願望の倒錯の物語であるともとれるのである。
結局、この映画の面白さとはその二面性である。つまり、幽霊である奈々瀬の願いとしての「幽霊譚」と倒錯した「岸辺露伴の主観」である。
ただ、そういった「二面性」の間にこそ怪談が存在しているのであり、「岸辺露伴ルーヴルへ行く」の面白さはその二面性そのものにある。
以上、色々考えた私の感想でした。皆さんはどんな感想をもったでしょうか。そもそも「つまらない」と思ったかもしれませんが、まあ、そんなこともありますよ。
この記事を書いた人
最新記事