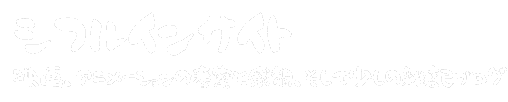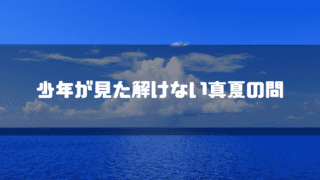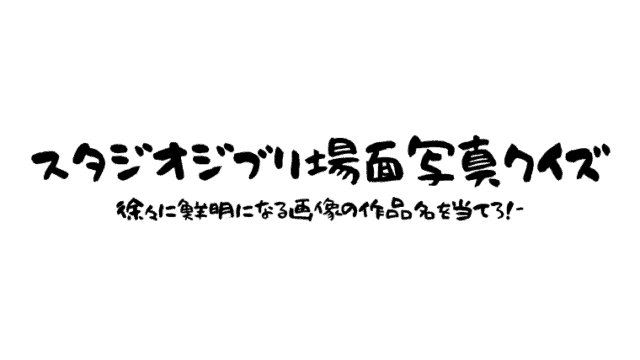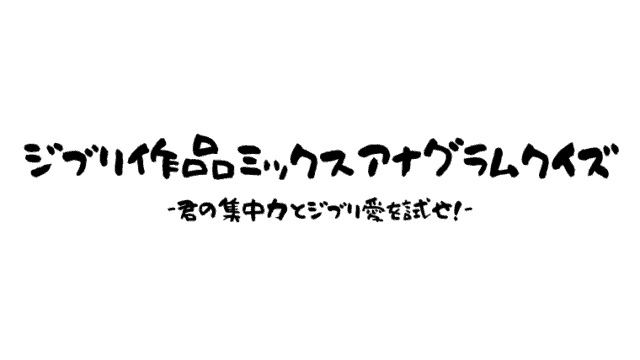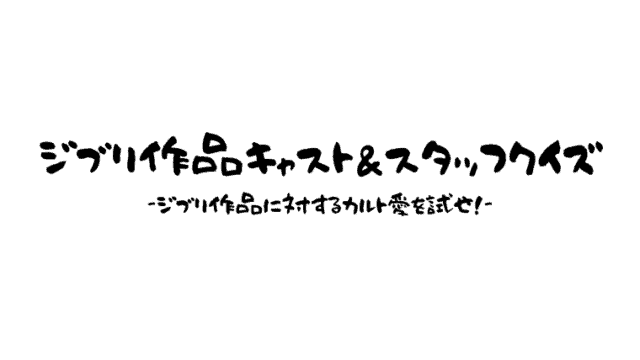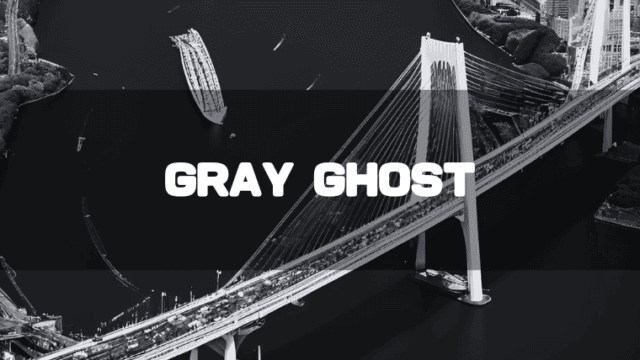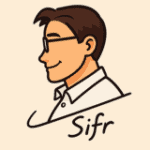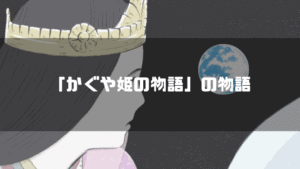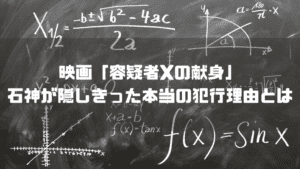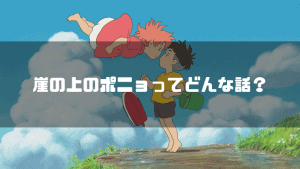「ぼくらの七日間戦争」は1988年8月13日に公開された菅原比呂志監督による劇場作品である(原作1985年4月発行された宗田理の同名小説)。宮沢りえの俳優としてのデビュー作でもあった。
初めて見たのは小学生の頃で、「戦車が登場する」という唯一点においてこの映画が好きだった。
ところが中学生、高校生、大学生、おっさんと年齢を重ねるたびにこの映画に対する心象が変わっていった。それはつまり「ぼくらの七日間戦争」が良い映画であるということなのだが、今回は心象の変遷についてまとめた上で、「ぼくらの七日間戦争」とはどういう作品だったのかを考えていこうと思う。
まずはあらすじを振り返ろう。
-
肩入れする対象の変遷
最初は主人公たちに共感しにくく、むしろ教師やほかの生徒に同情していた人も、 年齢を重ねるにつれ「状況に反抗する子どもたち」の行動が理解しやすくなる。 物語を観る側のライフステージによって、応援する立場が変わっていくのが 大きな特徴となっている。 -
校内暴力・受験戦争による管理体制への批判
1970年代後半から顕在化した校内暴力や、共通一次試験の導入に伴う 受験戦争の激化が作品の背景にあり、管理一辺倒の学校や詰め込み教育への 批判が物語の基底となっている。しかし、その後の社会の変化により、 当時のような管理体制は現在では実感しづらい部分がある。 -
弱者化する教師たちと「主人公でない生徒」への視点
90年代以降、教師への風当たりは強まっていき、かつてのような 強力な管理体制は後退。主人公以外の生徒からすると、 「勝手に立てこもられて迷惑」という見方も生まれ、 作品を観る時期や立場によっては教師や周囲の生徒を支持する心理が働く。 -
「火垂るの墓」との対比と“戦車”の役割
本作の主人公たちは、状況に不満を抱えつつも 戦車という“決定打”を得て短期的に爆発し、最終的に日常に回帰できる。 一方で「火垂るの墓」の清太のように“戦車”を持たず 破滅へ向かうケースもあるため、本作は「ここではないどこか」へ逃げたい という気持ちを肯定しつつ、きちんと着地点を用意している点が際立つ。 -
ホームレスの存在が示す“人間性”
廃工場に居ついたホームレスを、主人公たちは追い払わず、 むしろ一緒に食事を分け合う。直接ストーリーを左右しないように見えるが、 彼とのやりとりが「学校を飛び出した生徒たちは根っからの無法者ではない」 という人間性の証明になっており、物語を支える重要な要素といえる。
「ぼくらの七日間戦争」のあらすじ(ネタバレ有り)

簡単なポイント
-
廃工場での集団家出と自由の謳歌
中学1年A組の男子8名が受験戦争や学校の管理体制に反発し、 廃工場に籠って自由な生活を始める。途中で女子3名も加わり、 物資の持ち寄りやリフォームで理想的な共同生活を満喫する。 -
戦車「エレーナ」の存在と深まる対立
学校側の説得を退けるため、生徒たちは廃工場内で放置されていた 戦車を修理・運用し、教師陣を撃退。事態が警察・機動隊の介入へ発展し、 “籠城”は一気に社会的な騒ぎに拡大していく。 -
最終決戦と新たな決意
生徒たちは籠城戦の中で機動隊の強行突破を巧妙な作戦でしのぎ、 地下道から脱出。最後に仕掛けた花火が廃工場を美しい炎で包む。 戦いの後、彼らは「次は国会議事堂だ」と、さらなる行動を誓って日常へ戻る。
ここからはもう少し詳しく「ぼくらの七日間戦争」のあらすじを見ていこう。
エスケープ
物語は青葉中学の同じ1年A組に通う8名の男子生徒達による「家出」に始まる。彼らは日頃から学校側の管理体制や受験戦争に嫌気がさしていた。そんな5月のある日、授業を抜け出した彼らはそれぞれに物資を持ち寄って廃工場に集まり、そこで集団生活を始める。
翌日、彼らの母親が「集団家出」であると学校側に抗議をするが「生徒個人か家庭の躾が悪い」と一蹴されてしまう。
そんな中、男子生徒たちは着々と廃工場の「リフォーム」を進めながら「自由」を謳歌していた。また、同じクラス学級委員を含むの女子生徒3人も彼らの応援に駆けつけ、全ては目論見の通りに進んでいた。
しかし、廃工場にいる生徒を見たという連絡が学校に入ってしまう。
守護神エレーナ
生徒達の行動を軽く見ていた学校側は、教師数人と生徒の母を連れて廃工場を訪れるが、爆竹、モデルガン、消化器、セメント弾、放水等の苛烈な抵抗を受け、彼らを連れ戻すことに失敗してしまう。
生徒達は次なる「襲撃」に備えて準備を進めるが、その折廃工場に放置された戦車を発見。戦車の整備を始める。
一方その頃、内申点などを気にする1年A組の生徒達は学級委員に「なんとかしろ」と詰め寄っており、同じ境遇にいいても8人の男子生徒に共感するものばかりではないということが浮き彫りになっていく。
そして、なんとか出来るはずもないことを理由に詰め寄られた学級委員は、友人である2人の女子生徒を連れて少年たちに合流することを決めるのだった。
女子生徒が合流した翌日の朝、学校側は本格的な介入を始める。
工場内への教師の侵入を許してしまった生徒達はギリギリまで追い詰められるが、そこの工場の奥底で眠っていた戦車が現れる。
二人の男子生徒が操縦する戦車は瞬く間に状況を変え、教師達は退散していくのだった。学級委員長はその戦車に「エレーナ」と名付けた。
戦車によって教師たちを退散させたことまでは良かったが、事態は急変、警察が介入する騒ぎとなる。
一方でエレーナはエンジンの不調によって稼働不能となってしまった。また、事態の重さを生徒達も認識しており、次の「襲撃」を受けてしまえば全てが終わることを理解していた。彼らも最終決戦の準備を着々と進めるのだった。
最終決戦に打ち上がる思い
最期の戦いはもはや「生徒と教師」「子供と親」を超えて「籠城するものと機動隊」との戦いとなった。
警察も籠城を辞めるように説得するが、生徒たちは応じなかった。
そして、機動隊の突入が始まる。
籠城する生徒達は機動隊の攻防を続けるが、徐々に追い詰められていく。しかし、その姿はまるで追い詰められたいようでもあった。
籠城する生徒達が巧みに設置した罠に機動隊の面々がハマっていく中、ついに強硬派の教師もその状況に参戦する。しかし、その状況ですら生徒の想定を超えていなかった。
機動隊と教師の進行を食い止めた生徒達は、すでに発見していた地下道を通って廃工場の外へ逃げ出していた。
生徒達の目的はすでに籠城でも迫りくる脅威の排除ではなく、自分たちの行動の有終の美を飾ることであった。そんなとき、彼らがエレーナに設置した時限装置によって花火が起爆される。
多くの混乱を巻き起こした廃工場は、美しく燃えがる炎に包まれていた。
…
全てが終わり、日常に帰った生徒達は「次は国会議事堂だ」と決意を新たにするのだった。
「ぼくらの七日間戦争」の考察

肩入れする対象の変遷
「ぼくらの七日間戦争」を見る場合、我々が肩入れする対象は主に4つあるだろう。つまり、
- サボタージュを決めた主人公達、
- 学校の教員、
- 主人公たちの親、
- その他の生徒達
である。この中で物語の作りてが肩入れしてほしいと思うのは当然「サボタージュを決めた主人公達」ということになると思うのだが、私の人生を振り返ると、肩入れしていたのは順番に、
- 戦車
- 学校の先生、
- その他の生徒達、
- サボタージュを決めた主人公達、
- 主人公たちの親
だった。しかもそれぞれの変遷の間に結構な時間が存在している。
戦車についてはどうでも良いのだが、戦車のあとに肩入れしたのが「学校の先生」ということが少し重要であると思う。
それを考えるために、まずは「ぼくらの七日間戦争」の前提となる「校内暴力」と「受験戦争」という問題を振り返っていこうと思う。
前提となる「校内暴力」と受験戦争
「校内暴力」への対応としての管理体制
私が学校の生徒として日々を過ごしたのは90年代から2000年代である。高校生の頃には出来の悪い小テストを窓の外へ投げ捨てる教師はいたのだが、「ぼくらの七日間戦争」で描かれるような徹底した管理体制とは程遠いものであった。
そもそも「ぼくらの七日間戦争」で描かれる教師があれほどまでに生徒を管理しようとするには1970年代後半から顕在化した所謂「校内暴力」の問題がある。
「校内暴力」の問題は「3年B組金八先生」や「スクールウォーズ」で描かれたが、生徒同士あるいは生徒から教師への暴力が大きな社会問題になっていた。
学校としての対応策の一つが徹底した管理体制の構築だった。ただ、その結果として教師から生徒への暴力も発生することになる。
原作の小説が発行された1985年あたりから「校内暴力」の件数は減っているのだが、その裏にある学校の管理体制への不満も膨れ上がっていたことになる。
そういう状況の中で公開されたのが「ぼくらの七日間戦争」であった。
そして1990年には以降の状況を蹴って付ける「神戸高塚高校校門圧死事件」が発生。学校の管理体制は否応なしに見直されることになる。
私が生徒としての日々を過ごした段階で、「ぼくらの七日間戦争」的管理体制を経験しなかったのはある意味当然のことであったということになる。
苛烈な「受験戦争」と「詰め込み教育」
「ぼくらの七日間戦争」明確に批判するために描かれているのが所謂「詰め込み教育」そして「受験戦争」である。
1979年に共通一次試験が導入されているが、その理由の一つに大学入試の難問・奇問化があった。つまり、真面目に高校3年間頑張った生徒の能力を正しく評価できていないという批判があったということになる。
逆に言うと大学受験は苛烈を極めていたということなのだが、共通一次試験の導入によって受験戦争はより苛烈化したという見方もある。共通一次試験で失敗して足切りを食らったらそこで終わりなわけですから、手を抜けないわけで、その上で二次試験があるのだから苛烈化するのは当然とも言える。
その一方で、おそらくは「詰め込み教育」への批判として「個性を重視」とか「生きる力」の大切さが取り沙汰される事となり、90年代はその変化の真っ只中にあった。
それもあってか、それほど詰め込み教育を受けた記憶がない。正確に言うとまったくない。
このように、「校内暴力」に端を発する学校の管理体制や「詰め込み教育」の批判はそれ以前の状況が前提となっており、「ぼくらの七日間戦争」を子供時代に見た人間にとってはある意味ピンとこないことが描かれているという状況でもあったと言えると思う。もちろん、地域差や個人差はあると思うが。
このように振り返ってみると、私が子供時代に「教師」という存在に肩入れできた理由も見えてくる。
立場が弱くなる教師たち
ここまで振り返ってきたように、「ぼくらの七日間戦争」のような映画、小説が生まれる背景には「校内暴力」や「受験戦争」を背景とする「管理体制への批判」があるのだが、そんなフィクションが作られるくらいなので90年代に入ると教師と生徒との関係背はどんどん変化していくことになる。
私は小、中、高と地方の公立の学校で過ごしたが、強烈な「管理体制」や極端な「受験戦争」を感じることはなかった。もちろん私が鈍感なだけだったかもしれないが、特段教師が校則について厳しく追求することはなく、そこにあったのは「一応先生の言うことは聞くものであろう」という緩やかな感覚だったと思う。
そのような中で「ぼくらの七日間戦争」を見れば「先生も大変だな~」と子ども心に思うもので、「立てこもったって何にも変わらんだろ~」とむしろ主人公たちに批判的ですらあったと思う。
さらに、2000年代以降はどんどん教師に対する風当たりは強くなる。今や学校の先生のほうがある種の「弱者」に回っている節すらあり、それに伴って教員の数もバンバン減っていった。
「ぼくらの七日間戦争」は70年代から80年代という時代が生んだ物語であり、おそらく現代的には成立し得ない。そしてその変化のさなかにいたからこそ、私はまずは教師に同情したのだと思う。
また、それに伴い、主人公以外の生徒に対する同情も自然と生まれてくる。自分という存在は特段教師に抑圧を受けたこともないし、かつてのような死に物狂いの受験も経験していない。私が感情移入できる生徒達はどう考えたって主人公たちではなくその他の生徒ということになる。
主人公たちのために学校のリソースが割かれるわけだから「いい迷惑」と考えたわけ。
以上のような理由から、私はまず教師とその他の生徒達に肩入れしながら「ぼくらの七日間戦争」を見ていたと思われる。
歳を重ねたほうが主人公たちに同情できる
まずは「教師とその他の生徒」に肩入れしていた私だが、年齢を重ねるにつれてその状況は変わっていく。
私が主人公に肩入れできなかった理由を一言でまとめると「それほど状況に不満がなかったから」ということも出来るだろう。
しかし、年齢を重ねていくと状況に対する不満も溜まっていくもので「ここではない何処かへ」と考えてしまうことだって増えてくる。そうなってくると「ぼくらの七日間戦争」の主人公たちの見え方もわずかずつ変わっていくもので「なかなか頑張ったじゃないか」と今では思う。
「生徒が学校、教師、親に反抗する」と具体的な対象として考えるのではなく「状況に対する不満」に対して「行動」を起こしたというところまで抽象度を上げれれば、共感もしやすいだろう(もちろん「フィクション」であることは前提に)。
これは尾崎豊の「15の夜」にも同じことが言えると思う。盗んだバイクで走り脱すようなやつは死ねばいいが、「盗んだバイクで走り出すという歌」は名曲であり得るわけである。これもつまりは「ここではない何処かへ」ということなのだから、社会に揉まれている大人のほうがむしろその気持はわかる。
そして主人公たちの「状況に対する反抗」を見るとき、どうしても私は「火垂るの墓」の清太を思い出してしまう。
途中で辞めることが出来た「火垂るの墓」
高畑勲監督作品である「火垂るの墓」といえば、太平洋戦争集結直前から直後を描いた作品である。その概要は以下の通りである:
主人公である14歳の少年である清太は神戸大空襲の後に母を失い4歳の妹の節子と共に叔母の家に厄介になるのだが、関係が極度に険悪になってしまう。清太は節子と二人で近場にあった横穴(防空壕)で二人だけの生活を始めてしまうが、結局妹の節子は栄養失調からくる衰弱によりなくなり、その1ヶ月後の昭和20年9月21日、清太も同じ理由でなくなってしまう。
事の顛末、特に節子の死があまりにも悲しく多くの人にとって「一生に一度見て、一度しか見ない映画」となっていると思う。
さらに、終戦直前の極めて困難な状況で「子供二人での生活」を始めてしまった清太に対して節子の死の責任を追求する流れもあり非常に厄介な物語となっている。

だた、「火垂るの墓」における清太の行動も「戦争の混乱」や「妹への責任」という具体性を離れて「自分が作ったわけではない不条理な場への反抗」くらいまで抽象度を上げることができれば、子どもなりに出来る限りやったくらいには思えるかもしれない。
それでもなお問題となるのは節子の死であり、清太本人の死となる。つまり清太は行き着くところまで行ってしまった。
一方で「ぼくらの七日間戦争」において、主人公たちの闘争はちょうどいいところで終わってくれて、彼らは日常に復帰する。もし彼らが日本中、あるいは世界中をさまよい続ける物語になっていたら全く印象が変わったと思う「おいおい、この期に及んで学生運動の夢かよ」と。
つまり、主人公たちの戦いの場は日常の中に見出されるものに回帰したことになる。映画は「次は国会議事堂だ」という台詞で終わるのだが、それはつまり「状況に不満があるのならそれを順手で変えていこう」という宣言であろう。別に「国会議事堂襲撃」を画策しているという意味ではない。
願わくば「火垂るの墓」の清太も、彼らと同じ道を歩んでほしかったと「ぼくらの七日間戦争」を見るたびに私は思う。
彼らの守護神としての戦車に清太を思う
「火垂るの墓」との比較をする上で実のところ最重要となる要素が戦車の存在である(Wikipedia情報によると原作に戦車がないことも面白い)。
「ぼくらの七日間戦争」における闘争が何故終わることが出来たのかということを考えると、彼らが正しく爆発できたからということが出来ると思う。
彼らの行動はバレてしまえば直ちに終わりを告げるし、物資の不足からバレなくても終わりを告げてしまう。そんなことは彼らも承知で始めたことだろう。しかし、そのような必然としての終焉を迎えたところで彼らの中にはなにか満ち足りたものが残るだろうか?おそらく残らない。そこに残るのは「失敗」という思いである。そこには「終わり」がないのである。
何かを終わらせるためには「理由」が必要となる。戦車エレーナは彼らにその「理由」を与えてくれたのだろう。その理由を端的に述べれば「一発食らわせたやった」ということにことになると思う。
それは、戦車の脅威に慄く姿を見ることが出来たということでもあるし、花火を打ち上げてやることによって「どうだ!」と状況が思いもよらないことをやらかしてやったということでもある。
とにかく、戦車という存在が状況を収束させてくれたということが出来るだろう。
しかし、映画「火垂るの墓」の清太には戦車がなかった。つまり、彼に残されたのは必然としての破滅だけであった。彼にも「ぼくらの七日間戦争」の主人公達と同じような「戦車」があれば、状況は変わったのかもしれない。
どうしても「ぼくらの七日間戦争」を見ると「火垂るの墓」を思い出してしまうね。
以上が「ぼくらの七日間戦争」について個人的に考えたことの全てとなります。良い映画とは若い頃に見た映画であり、見るたびに新しい発見があるものだとお思いますが、そういう意味で、この映画は傑作といってよいのだと思います。
おまけ:瀬川卓蔵(ホームレス)の謎
「ぼくらの七日間戦争」をただ見ているだけなら対して疑問が沸かないように描かれているのだが、よくよく考えると不思議なのが廃工場にいたホームレスの存在である。
彼はいてもいなくても物語には全く抵触しない。にも関わらず何故かそこに存在している。
その理由を言語化してみると、それは、廃工場に立てこもった生徒達の人間性を保証する存在ということが出来るのではないだろうか。
彼らは確かに通常の道を外れたのだが、根っからのならず者ではない。そこにいるホームレスを排除することもなかったし、いじめることもなかった。そればかりか自分たちが作った食事をお裾分けすらしていた。
一見いてもいなくても変わらない存在としてのホームレスだが、エスケープを決めた生徒達の人間性を保証する存在として見事に機能していたと思う。
「ぼくらの七日間戦争」のキャスト&スタッフ一覧
| 監督 | 菅原比呂志 |
|---|---|
| 脚本 | 前田順之介、菅原比呂志 |
| 原作 | 宗田理 |
| 制作 | 角川春樹 |
| 音楽 | 小室哲哉 |
| 主題歌 | TM NETWORK「SEVEN DAYS WAR」 |
| 菊地英治 | 菊池健一郎 |
|---|---|
| 相原徹 | 工藤正貴 |
| 安永宏 | 鍋島利匡 |
| 柿沼直樹 | 田中基 |
| 日比野朗 | 金浜政武 |
| 中尾和人 | 大沢健 |
| 天野健二 | 石川英明 |
| 宇野秀明 | 中野慎 |
| 中山ひとみ | 宮沢りえ |
| 橋口純子 | 五十嵐美穂 |
| 堀場久美子 | 安孫子里香 |
| 榎本勝也 | 金田龍之介 |
| 丹羽満 | 笹野高史 |
| 酒井敦 | 倉田保昭 |
| 野沢拓 | 大地康雄 |
| 八代謙一 | 佐野史郎 |
| 小柳 | 小柳みゆき |
| 西脇由布子 | 賀来千香子 |
| 菊池英介 | 出門英 |
| 菊地詩乃 | 浅茅陽子 |
| 菊地まりこ | 穴原英梨 |
| 相原徹の母 | 恵千比絽 |
| 安永宏の母 | 田岡美也子 |
| 柿沼直樹の母 | 宗田千恵子 |
| 日比野朗の母 | 船場牡丹 |
| 中尾和人の母 | 沢井孝子 |
| 天野健二の母 | 竜のり子 |
| 天野健二の父 | 石川清 |
| 宇野秀明の母 | 西海真理 |
| 橋口純子の母 | 正国秀子 |
| 堀場久美子の母 | 三田佳子 |
| 堀場久美子の父 | 粟津號 |
| 瀬川卓蔵(ホームレス) | 室田日出男 |
| アナウンサー | 上柳昌彦 |
| リポーター | リポーター |
| ラジオDJ | 三宅裕司 |
この記事を書いた人
最新記事